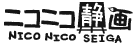せんとうき を含むイラストが 19 件見つかりました ( 1 - 19 件目を表示 ) タグで検索
パイロットwww これがイカん砲・・・ イカ「おれと合体しろ なにやってんだw そうかこういう仕組み なんつーアグレッシブ 逃れられない通過儀礼 あたりめ!!
ていうかこれ4発機じ 双発機のエンジン云々 ↑↑お前自分の発言が相 ↑それ言ったら単発機 エンジン一発止まった どっちも止めちゃえば 左右どちらかのエンジ 三面図欲しいな
(れいしきかんじょうせんとうき: 以下、零戦)は、大日本帝国海軍(以下、海軍)の主力戦闘機。皇紀2600(西暦1940)年に制式採用され、末尾の00で「零式」の型式が付いた。(九六艦上戦闘機は皇紀2596年採用のため末尾の96を取って九六式)海軍の艦上戦闘機(以下、艦戦)としては実質的な最終型式で、支那事変の半ばから大東亜戦争(太平洋戦争)の終わりまで各地で活躍したことで知られる。大東亜戦争初期に連合国の戦闘機を駆逐したことから、主交戦国のアメリカ軍から「ゼロファイター」(コードネーム「Zeke」)の名で恐れられた。 このゲームではCFS2と異なり、vulnerableオプションの設定に関わらず零戦などの7.7ミリ機銃がかなり冷遇されており、グラマンなど防弾が施された機体には機関部やコクピットなど致命部にピンポイントで打ち込まないと手ごたえがほとんど無い。ほぼ無反動なので射撃安定性が高いのが救いだが、20ミリを極力使わない坂井三郎ごっこは無謀。
九一式戦闘機(きゅういちしきせんとうき)は、第二次世界大戦前の日本陸軍最初の単葉戦闘機であり、陸軍初の日本オリジナルの設計による戦闘機である。呼称は九一戦、九一式戦。複葉の甲式四型戦闘機に代わって制式機となった。中島飛行機がフランスから招聘したアンドレ・マリー技師を中心に設計され、中島飛行機によって製造された。1932年より1935年頃の日本陸軍の主力戦闘機であった。
せあのもったり放送 - co1167784 - でやっているしりとりの絵です。 「ん」で終わる単語はその一文字前の文字からつなぎます。 ぱいろっと→とうじょう→うちゅうせん→せんとうき→ききゅう→うきわ→わたあめ→めじろ→ろうば→ばーこーど→どりーむ→むーむー→むぎわらぼうし→しっぽ→ぼりばけつ→つつ→ついらく→くせもの→のうみん→みけ→け→けるべろす→すぽんじけーき→きけんじんぶつ→→つまさきだち→ちか→かげ→げんえい
ジェットせんとうきに まけない スピードで そらを とぶ。ねらった えものは にがさない。 ポケモン図鑑制覇を目指しています! 週末の昼間に消しゴムはんこ彫り放送をやることがあります。 アホップルの消しゴムはんこ講座 co519403 アツタメガネというボカロPの動画に、消しゴムはんこで参加させていただいております。 よければどうぞ。 アツタメガネのマイリスト mylist/18459782
キ27 中島九七式戦闘機(なかじま97しきせんとうき)は、1940年前後の大日本帝国陸軍の主力戦闘機で、陸軍最初の低翼単葉戦闘機。旋回性が非常に高く、格闘戦では右に出る機体は無かったと言われる。ノモンハン事変ではソ連空軍を相手に戦い、一部は太平洋戦争初期まで運用された。しかしここでは敵よりも大幅に低速で、一撃離脱戦法をとられると対処できなかった。護衛すべき爆撃機に追いつけず護衛に失敗するという失態もあり、早々に一式戦闘機に置換された。九七戦もしくは九七式戦と略称されることもある。連合国によるコードネームはNate。
(96しきかんじょうせんとうき)三菱A5Mは、日本海軍最初の全金属単葉戦闘機。ほぼ同時に設計・製作された九六式陸上攻撃機と並んで、日本の航空技術が欧米各国の模倣を脱して、日本独自の優秀機を製作し始めた最初の機体。後継機は零式艦上戦闘機。なお、連合軍のコードネームは「Claude」。
三式戦闘機(さんしきせんとうき)は第二次世界大戦において用いられた日本陸軍の戦闘機で、紀元2603年制式採用により三式戦闘機と称した。日本軍機にしては高々度性能が良かったが、エンジンが機体重量のわりにアンダーパワー気味で上昇性能は低かったとされている。 陸軍からドイツのDB601を搭載した重戦闘機と軽戦闘機の開発を指示された川崎飛行機は重戦闘機のキ60と速度と運動性を両立させた“中戦”思想の機体としたキ61を開発し、キ60はキ61が高性能だったのと性能に不満があったため開発中止となった。ド-リットル隊による東京初空襲では試作機が迎撃に上がりエベレット・w・ホームストロム少尉機を捕捉、攻撃したが徹甲弾しか装弾していなかったため撃墜には至らなかった。 整備兵が液冷エンジンに不慣れだったことも手伝ってエンジントラブルが多発し、散々な悪評を浴びることになった。整備兵の教育と予備部品の供給が可能だった本土防空隊では、比較的高い評価を受けている。 形式番号はキ61で愛称は飛燕(ひえん)である。連合軍のコードネームは『Tony』。
五式戦闘機(ごしきせんとうき、キ100)は太平洋戦争に用いられた大日本帝国陸軍の戦闘機で、開発・製造は三式戦闘機とおなじく川崎航空機(現:川崎重工業)である。 三式戦の空冷化は昭和18年ころから提案されていたが発動機を高出力のハ140に換装するなどした三式戦闘機二型改が生産され、ハ140の故障続発と生産の遅延により機体が374機生産されたのに対して飛行できたのは99機のみで残った“首なし飛燕”が現れたことでようやく開発されることとなった。発動機をハ112Ⅱに換装してドイツのFw190のように推力式単排気管を並べることで大口径の空冷発動機を収めることに成功し、速度は低下したが重量が軽くなったため旋回性、上昇力などが向上した。稼働率が高く機体性能もそこそこよかったため陸軍の白眉なったが登場が遅い上に本土決戦に向けて温存策が取られたため極短期間のみ限定的に使用されたことになる。
一式戦闘機(いっしきせんとうき。以下、一式戦)は旧日本陸軍の太平洋戦争(大東亜戦争)前半における主力戦闘機。愛称は「隼」(はやぶさ)。 当初は九七式戦に格闘性能が劣るとされ採用が危ぶまれたが南進に即して航続距離の長い戦闘機が求められたたため採用された。そのため開戦時には僅かな数が配備されていたに過ぎず九七式戦が主力として使用された。 アメリカ軍がつけたコードネームは「Oscar」だが実際は海軍の零戦と区別がしにくいと言うことで「01」とも呼ばれていた。 初期の一型は軽量化しすぎのため主翼の桁が弱く、急降下からの引き起こしで空中分解したり主翼に亀裂が入る事故がいくつか発生した。また12.7mm砲も当初は信管の信頼性が低く暴発の危険があった。 二型以降はエンジン出力の増加や翼幅を短くし桁を強化するなどの改修が行われたが、構造上主翼に武装ができないため火力は低いままだった。しかしながら、後期になるほど運動性の低下していった零戦と違い、最後まで軽戦闘機としての運動性を保っていたため、連合軍からは、低空では油断できない相手として警戒されていた。実際ビルマ戦線では末期までキルレシオで連合国新鋭機に対して勝っていた。また日本のパイロットにも、回避運動がしやすく信頼性の高い隼(三型)を、重戦闘機の性格の強い疾風より高く評価した者は多かったという。