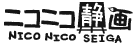アメリカ陸軍 を含むイラストが 124 件見つかりました ( 101 - 120 件目を表示 ) タグで検索
XP-56 ブラックバレットは、アメリカ合衆国のノースロップ社が試作した戦闘機である。単発の推進式レシプロエンジンを胴体後部に配置して二重反転プロペラを駆動し、形状的には無尾翼機であるという特異な機体であった。安定性不良等の問題が多かったこともあって、2機の試作のみに終わった。
39年の大戦勃発後、イギリスよりP-40のライセンス生産を依頼されたノースアメリカン社は、120日以内にP-40と同じエンジンでより高性能な戦闘機を開発すると逆提案し、突貫作業で設計を進めた。層流翼を始めとする最新技術を取り入れ、40年5月29日の契約から117日で完成した試作1号機は優秀な性能を示し、ムスタングMk. Iとしてイギリス空軍に採用された。アメリカ陸軍は当初無視していたが、参戦後の再テストで優秀性に気づき、わずかな変更を加えてP-51A(英名ムスタングMk. II)として採用した。 この初期型ムスタングは低空ではスピットファイアL.F. Mk. Vより高速であり、操縦性も良好、特に航続距離は群を抜いていた。一方で重量がかなり重いため上昇力が低く搭載したアリソンエンジンのため高々度性能は貧弱であり、もっぱら地上攻撃機として用いられた。しかし、ロールスロイスのテストパイロットの提案により、マーリンエンジンに換装すれば飛躍的な高高度性能向上が見込まれることが分かり、イギリス・アメリカ双方で改造が行われた。42年末に行われた試験飛行の結果は予想を上回るもので、直ちに大量生産が開始された。後に視界と火力を改善した最多生産型のP-51Dへと発展し、第2次大戦における最優秀戦闘機となった。 欠点としては、胴体内燃料タンクに燃料を積むと重心が後退して運動性が極度に悪化する事、旋回しながら射撃すると翼内機銃が装弾不良を起こしやすい事(機銃が傾けて搭載されていたため)などが報告された。前者は増槽より胴体内タンクを先に使うことで防止していたらしい。後者は、D型で主翼を再設計するさいに改善された。
アメリカ陸軍はお母さんの病気を治すことを意識しているまみたちのある噂が戦闘機に入ってきたのです それは大会に優勝して希望の女神像をP-51やP-47などがもらうからだ
P-75は、アメリカ合衆国の自動車メーカーのゼネラル・モータースのフィッシャー・ボディ部門が、アメリカ陸軍航空軍向けに開発した戦闘機である。愛称はイーグル。初飛行は1943年11月17日。試作機と量産機合わせて12機生産されただけで開発は中止になった。
シコルスキー S-58(Sikorsky S-58)は、アメリカ合衆国の航空機メーカー、シコルスキー・エアクラフト社が開発したヘリコプター。シコルスキー S-55の機体を大型化し、エンジン出力も増大して実用性を高めた機体である。日本をはじめ世界各国へ輸出、イギリスやフランスでも生産が行われることで、全世界で2,261機が製造されるベストセラー機種となった。 S-58は同社の社内呼称であるが、販売にもこの名称を使用していた。
ダグラス XB-19は、アメリカ陸軍航空隊向けにダグラス社が試作した爆撃機で1938年に試作機1機のみ建造された。当時としては最大規模の重爆撃機であった。同時期にボーイング社も同様に大きな機体を試作しており、そちらはXB-15である
YFM エアラクーダは、第二次世界大戦前にベル社がアメリカ陸軍航空隊向けに試作した戦闘機である。4発重爆撃機を護衛する目的で開発された双発機だったが、飛行性能が悪く、開発中止となった。 愛称の「エアラクーダ 」は、空飛ぶバラクーダの意。
M24チャーフィー軽戦車(英語:Light Tank M24)は、第二次世界大戦においてアメリカ合衆国が使用した軽戦車である。 愛称はアメリカ軍戦車開発のパイオニアであったアドナ・R・チャーフィー・ジュニア将軍にちなみチャーフィー(Chaffee)と名付けられた。
1935年に初飛行した、世界初の近代的4発重爆撃機。 機体の一部を失うほどの損傷でも飛行可能なほど、高い安定性と耐久性をもっており、対ドイツ昼間戦略爆撃に使用された。 大量の爆弾を搭載し長距離を飛行し越境攻撃が可能な「戦略爆撃機」として有名。武装や搭載量で各種の型式があり約12,000機も作られ、1968年まで現役で使用された。(ブラジル空軍)
35年にアメリカ陸軍の要請によって開発された単葉戦闘機。P-36として採用された他、フランス、イギリス、ノルウェー、オランダ、中華民国などに輸出された。しかし開戦までに旧式化し、ヨーロッパでも太平洋(オランダ)でも、より強力な敵に破れた。なおノルウェーでは輸入直後にドイツ軍の上陸が始まったため、実際には使用できなかった。 フランスとノルウェーがドイツに占領された後、両国のホーク75はフィンランドに提供され、第32戦闘機隊を編成した。機体性能ではバッファローに次ぐものだったが、錬度の差でバッファローほどの活躍は出来なかった。
1940年初飛行、連合国側を代表する双発中型爆撃機。本来ノースアメリカン自社設計の機体(NA-40B)であったが、戦線の拡大に伴い急遽正式採用された。約10,000機生産され1979年まで現役として活躍した。 武装を無くした特殊攻撃型で空母から発進し東京を初空襲した事で有名。 ソビエトにも870機が送られ、高く評価された。 各種の改造機体があり、75mm砲と12.7mm機関銃を8門も機首に配置した艦艇攻撃型や地上攻撃、偵察専門の機体もある。 愛称のミッチェル(Mitchell)は、在仏米陸軍航空隊司令官として第一次世界大戦で武勲を上げ、アメリカ空軍の父とも呼ばれているウィリアム・ランドラム・ミッチェルにちなんだもの。
セスナ社のベストセラー単発機モデル170シリーズのうち最初の成功作となったモデル172を ベースとしたレシプロ練習機。 モデル170で不評だった尾輪式降着装置を3車輪式に改めたため地上安定性が向上しており、民 間向け小型機として1,000機以上の売り上げを残している。米国空軍は1960年代初頭に(ベ トナムでの軍事行動を見込んで)新たな操縦練習機を必要としていたため、緊急にモデル172を導 入し、T-41Aの呼称で操縦練習機として使用した。また米国陸軍もT-41Bの名で当機を導入、 米軍だけで300機以上の機体が調達されている。 また米国が行うMAP(軍事援助計画/詳細は当サイト 用語辞典を参照)においても同盟国へ供与 される機体として226機が調達され、同盟諸国へ供与された。
B-26 マローダー(Martin B-26 Marauder)は、マーティン社が開発し、第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空隊で運用された爆撃機。 米陸軍航空軍における愛称の「マローダー(Marauder)」とは、「略奪者」の意である。同時期に開発されたB-25 ミッチェルより、高速性能などで勝っていたが、操縦の難しさから初期型では事故が多発し、乗員には「マーダラー(人殺し)」「キラー・プレイン(殺人機)」「ウィドウ・メーカー(未亡人製造機)」と呼ばれて嫌われた。その結果、B-25に比べて生産数や運用国の数で大きく差がつく結果となった。
アメリカ初の実用ジェット戦闘機。1944年に試作機初飛行、1945年春には訓練部隊に配備開始となったが、WWII中に実戦参加することは無かった。 ロッキード社の奇才設計技師「Clarence Leonard "Kelly" Johnson」の手による設計。彼はのちにロッキード社の副社長まで上り詰め、スカンク・ワークス・チーム(先進秘密開発設計チームの愛称)の主催者として有名。 彼の手がけた飛行機は、PV-1輸送機,P-38戦闘機,P-80,XF-90,F-94,P-2V対潜哨戒機,有名所ではF-104やC-130,U-2,SR-71他にF-117まで設計している。 1947年以降は米国空軍への再編成に伴い呼称がP-80からF-80に変更された。 朝鮮戦争が初の実戦機会となったが、直線翼でジェットエンジンの出力も十分でなかったことからアメリカのF-86・ソ連のMiG-15など後退翼の新鋭機に対して戦闘機としては既に時代遅れとなっており、地上攻撃用の戦闘爆撃機や写真偵察機としての用途で活躍した(Stock機体には爆装できず、MOD機体でプレイ可能となる)。 本機の胴体を延長してタンデム複座とした練習機T-33はジェット戦闘機パイロットの養成に都合がよく、P-80の3倍以上の生産数に達して長年に渡り使用されることになる。 またそのT-33をベースにしたF-94全天候戦闘機は、ジェットエンジンのインテークが胴体側面にあり機首に大型レーダーを搭載可能であったこと、複座でパイロットと別にレーダー手を乗せられたことが適任であった。
P-38ライトニングのエンジンを強化した試作戦闘機。 プラット・アンド・ホイットニーが開発中の2000馬力急液冷H型24気筒X-1800をP-38に搭載することで性能向上を狙った。しかし、このエンジンは開発に失敗。代替案としてコンチネンタル社製の液冷倒立V型XI-1430に載せ替えたが、こちらは1600馬力級で出力不足によってXP-49は所定の性能を発揮出来なかった。 更にXI-1430エンジンも結局開発中止になったことから、XP-49は不採用となった。
M1 エイブラムス(M1 Abrams)は、アメリカ合衆国が開発した主力戦車である。 エイブラムスの名は、開発を推進した人物であり、バルジの戦いの英雄でもあるクレイトン・エイブラムス大将に由来する。
リパブリック社(旧名セバスキー)が、ヨーロッパの戦訓から構想したターボ過給機装備・重装甲・重武装戦闘機。初飛行は41年。排気タービンとインタークーラーを後部胴体におき、胴体下と両側面にダクトを通してエンジンとつないだため太い胴体になった。その重さのため上昇力と旋回性は劣悪だが、高高度性能と急降下性能に優れていた。なお主翼内部はほとんどが弾薬庫であり、爆弾などを装備しなければ更に装弾数を増やすことができた。 42年末より第8航空軍に配備され、対ドイツ昼間戦略爆撃の護衛任務についたが、燃費が悪いためこの任務にはあまり適しておらず、P-51Bが配備されると対地攻撃にまわされた。この任務ではターボ過給機こそ無用だったが、絶大な搭載量と防御力で猛威を振るった。太平洋戦線に配備されたのは43年夏だが、護衛戦闘機にはP-51が使われたため、日本本土にはほとんど飛来していない。
AH-56 シャイアンは、ロッキード社によって1960年代に開発された、アメリカ陸軍向けの試作攻撃ヘリコプターである。愛称のシャイアン(Cheyenne)は、アメリカ先住民のシャイアン族に由来する。世界初の攻撃ヘリコプターとして開発されたが採用は取り消され、陸軍主力攻撃ヘリコプターの座はAH-1 コブラが得る事となった。