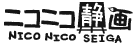ドイツ空軍 を含むイラストが 164 件見つかりました ( 121 - 140 件目を表示 ) タグで検索
ユンカースお得意の鋼管構造とジュラルミン波板による機体構造は軽い割に強度が保てますが、抵抗が大きくスピード面で不利でした。1930年代後半には旧式化しました。そこでJu 52の後継機として開発されたのがJu352です。アルミなど戦略物資を使用しない思想で全金属製から鋼管構造に合板と羽布張りの胴体、木製主翼の木金混合で、プロペラまでも木製(逆ピッチ可能)へと変更しました。しかし結果的には変更による重量増加により他国の輸送機に比べ性能的に劣っており、また戦況から戦闘機優先の生産の命令が出されたこともあり、生産数は50機どまりとなりました。ヘルクレスは、独語で「ヘラクレス」の意味。
アラドAr 96は第二次世界大戦時のドイツの高等練習機である。全金属製の単葉単発機で、密閉式のコックピットと引き込み脚を有する近代的な機体だった。1938年に初飛行した。 生産は前期型はAGO社で、後期型はチェコのレトフ社とアヴィア社で行われ、戦後もC-2という名称で数年間続けられた。合計1万1,000機以上製造されている。また、ハンガリーでも少数ではあるがライセンス生産された。
後退翼にT字尾翼、バブルキャノピーという先進的なデザインのジェット戦闘機。42年に開発が始まったが、45年4月に少数の試作機が作られた時点で工場が占領された。後の調査によれば、そのままの設計では強度が不足していたらしい。 MiG-15が開発される際に参考にされたと言われているが、ゲーム内の説明文では否定されている。
非常に高いSTOL(短距離離着陸)性能を持ちドイツ軍に大量使用された連絡/観測機 本来非常に地味な機種だが適当な平地であれば大抵離着陸可能なSTOL性能を持っていた(16mの向かい風があれば30mで離陸、16mで着陸可能)ため非常に重宝され、ムッソリーニ救出作戦などの数多くの武勇伝を持っている。敵国である英国陸軍元帥モントゴメリーが愛用するほど性能が優れていたため戦後にもチェコやフランスで生産が続けられ、日本ではFi156を参考にしたキ76三式指揮連絡機が生産された。
Me321はドイツのメッサーシュミット社が開発した大型輸送軍用グライダーである。 Ju52では不足する輸送力を求めて開発され、8.8cm高射砲とその牽引車、あるいは中戦車、120名の武装兵士などを輸送できた。 巨人を意味するギガントという愛称がつけられた。
メッサーシュミット Me 261 アドルフィーネ(Adolfine)は、1930年代末にメッサーシュミット社で長距離洋上偵察機として設計された、一回り小型のメッサーシュミット Bf110と同一レイアウトの航空機である。量産には入らなかった。
Bf109は、第二次世界大戦におけるナチスドイツ空軍の主力戦闘機。Me109とも呼ばれる。Bf109はまだ航空機が過渡期であった1934年にメッサーシュミット博士が開発したスポーツ機Bf108の経験を元に開発した機体であった。初飛行は1935年で、ハインケル社のHe112と制式採用の座を争ったが結果的にはBf109の勝利に終わった。1937年のスペイン内乱に際してドイツはBf109の初期生産型(680馬力Jumo210B/Dエンジン搭載のA及びB型)3個飛行隊を派遣した。この戦いではソ連の新鋭機ポリカプフI-16やI-15は敵ではなく、ドイツの撃墜王ウェルナー・メルダースが考案し、ドイツ空軍の御家芸となった2機編隊で集団を編成するロッテ戦法が考案されるなど、空中戦闘のノウハウを蓄積するにも役立ち、実戦経験を積ませることができた。そして第二次世界大戦が始まった頃には、Bf109はエンジンを大幅に強化し戦訓を取り込んだE型に切り替わりつつあった。 Bf109は日本の96艦戦などとほぼ同時期の開発であるにもかかわらず、E型・F型での大改修をへて、馬力をほぼ3倍に強化して終戦まで使用され続けた。しかし「小さな機体に馬力の大きいエンジンを」というコンセプトを優先し、他の部分が犠牲になったため、航続距離が短い、操縦席が狭く後方視界が悪い(実際はそこまで問題視はされておらず、手元に近いスロットル位置なども評価されている。)、主脚の強度不足(倒立エンジンはプロペラが低い位置に来るため、脚を長くする必要あった)と狭いトレッド幅、離着陸性能が極めて悪い、火力不足など欠点も多かった。 着陸性能の悪さと航続距離の問題は最後まで付きまとったものの、突っ込み速度は他の追随を許すことはなかった。直線番長に思われるが意外と低速での運動性は良く、逆に動翼が羽布張りのため高速時には痩せて、エンジンブレーキを使わないと操縦が効きにくくなる。 独軍機全般に言える事だが、計器の配列がとても分かりやすい配列になっており、Bf109の場合「右側に動力関係の計器」を、左側には「飛行関係計器をまとめて配置」されている。実際では各種ハンドル、スイッチの類もすべて手短な位置に設置されており、Bf109のテスト飛行をした連合国パイロットからも称賛されている。
Ju 86はドイツの航空機メーカー ユンカースが製造した、単葉の爆撃機 / 民間用旅客機である。排気タービン過給器付のディーゼルエンジン・与圧室・アスペクト比の大きな主翼を採用したJu 86Pは、第二次世界大戦の初期に高々度爆撃機・偵察機として成功を収めた。航空機用ディーゼルエンジンの歴史に残る機体である
戦闘機より速い爆撃機として開発された双発爆撃機だったが、戦闘機の高速化と航続力不足から爆弾槽を潰して燃料タンクとして爆弾は胴体に懸架され速度低下を招いたこともあり、当初の目的は果たせなかった。 しかし急降下爆撃可能な双発爆撃機として開発されたこともあり、主力爆撃機としてのみならず夜間戦闘機など非常に高い汎用性を見せた万能機として活躍した。
重装甲の双発単座地上攻撃機。 37年にドイツ空軍省が示した対地攻撃機の開発仕様は、生存性を高めるため可能な限り小型かつ重装甲、加えて双発であることを要求していた。更に武装も最低20mm機関砲2門となっていた。ヘンシェル社はこれに答え、操縦席からから燃料タンクまで6~12mmの装甲で覆い、風防は75mmの防弾ガラス、胴体断面形状は対空砲を避けるため三角とし、エンジンは小型のアルグスAs-410A(485馬力)空冷エンジン双発という試作機Hs129V-1を開発し、39年に初飛行させた。後にHs129Aとして量産されたが、全備重量5トンを越える機体としては非力すぎ、防弾ガラスと三角の断面形状のためコクピット内が異常に狭く(腰の位置で幅70cm、頭頂部で30cm)、運動性と視界と居住性は最悪であった。しかしフランス占領によりノームローン14M空冷エンジン(695馬力)が手に入り、これを装備して運動性を改善したB型が生産されることになった。ちなみに機体を極力小型化するため一部計器と照準器はコクピットの外に設置されている。 北アフリカではエンジントラブルによりあまり活躍できなかったが、東部戦線ではソビエト戦車部隊に対してかなりの戦果を挙げた。愛称はGiesskanne(ジョウロ)。空とぶ缶切りという呼び名もあるが、これは戦後のものらしい。
HFB320 ハンザジェット(HFB-320 Hansa Jet)は、1964年から1973年にドイツの航空機メーカーのハンブルガー・フルクツォイクバウで生産された全金属製、双発の10座ビジネスジェットである。
ハインケル He 116は、ドイツと日本の間で航空郵便を運ぶためにハインケル社で開発、製造された長距離郵便機である。この任務のために数機が、同様に長距離偵察機として少数が製造された。
ユンカース Ju 390は、Ju 290から派生したモデルで大型輸送機、洋上哨戒機、長距離爆撃機として使用されることを意図した航空機である。本機はお流れになったアメリカ爆撃機計画に提案された中の1機であった。