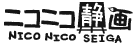一般的な 英語 を含むイラストが 5 件見つかりました ( 1 - 5 件目を表示 ) タグで検索
海外とかならsteamと ちゃっかり東方も海外 妹紅のオカルトアタッ 忘れられた都市伝説が 久々待ってました! 何故、衣玖が平仮名な 白黒版も見てみたいで ほーへー
ジェクトのあの剣に見 設定直してみた。ぎり エレメント系の属性追 ないと思うけど、炎っ あの、SAOって属性と よく調べたら属性っぽ ギリギリ剣技に…入っ 間違ってるかも
船路を描きたかったが‥‥ Note: 1000字書けるということで、唐突に、思い出したようなこぼれ話と雑感 ※絵と無関係 Sera-PersonとSera-Human:sm17714018の動画作成時、作中用語の英訳についてeplipswich氏の英訳版も参考にしました(当時もデモ版は公開されていたので)。で、英訳版で後者(Sera-Human)に変えたことには当時も気づきましたが、動画では原作と同じく前者にしました。これに関して私はいくつか観点があると思っています。まず、一般的な英語の用法として生物学的な意味でのヒトを指すのに使う、という意味ではHumanの方が適切だと思います。一方で、セラパーソンという種は単に「ヒトに似た生物学的別種」というのではなく、次の点が特徴的だと思います;a)パーソンの生活史を内包する形で彼らの生活史が成り立つこと(必ずパーソンという段階を経て、セラパーソンに至る)、b)パーソン時に培った精神的な蓄積を持つ点を種の優位性に位置づけていること。こうした観点からは、Personaを語源に持つPersonを用いることに一理あると感じます。こちらを重視して、動画はあのようにしました(当時の判断ですが)。なお、同じくヒトに近い人工生命体であってかつ上記のようなセラパーソンの特徴がないヴィルジニーに関しては、作中にてバイオ"ヒューマン"と表現されています。なので、天ぷら氏の意図は不明ですが、実際に前述のような観点を念頭に置いていた可能性もあるかもしれません。 雑: ・一章裏は、ココモ付近のユアンとWW付近のケインが、某家10年間の軌跡並に気になる。 ・無印→DCは、実際に比較をすると台詞変更点が意外と多く感じる(「言い回しが少し変わった」程度のものは、普通にリプレイしていると気づかなかったりするので、実際に差分確認した際に多く感じられたという話)。 ・無印→DCでのイベントシーン周りの主だった変更の多くは、何となく意図がわかる(OP/EDの流れや、某丘のランサードの推理など)。が、ケインの台詞が色々変わったことの意図はあまり分からないと、昔から思っている(大意は同じながらも重要シーンで変更割合が大きいので、結構印象が違う)。
山に横穴を掘って造る場合はトンネル状であり、平地に造る場合は鉄筋コンクリート製でかまぼこ型をしていることが一般的(少ない資材で大きな強度が得られるため)。第二次世界大戦時の日本軍は軍用機格納庫を兼ねた木造掩体壕も使った[1]ほか、爆風・破片除けの土堤のみで屋根(天井)が無い簡易な無蓋掩体壕もある。 掩体は、陸上自衛隊では「掩体」と漢字表記、航空自衛隊では行政文書上は「えん体」とひらがな漢字混じり表記、運用上は「シェルター」と現代アメリカ英語で一般的な表現をカタカナにして呼ぶ。第二次世界大戦期などは英語では主にbunker(バンカー)、ドイツ語ではブンカーと呼ばれ、ロシア語由来のトーチカと指す範囲がかなり重なっている。 航空自衛隊の航空機用のえん体は主に戦闘機の防護を目的に設置される。一般に格納庫は脆弱な鉄骨造だが、えん体は鉄筋コンクリート造であり、1機ずつ分散して格納することで防護能力を向上できる。航空自衛隊の戦闘機部隊は全国の7基地に配置されており、そのうち、千歳基地(北海道)、三沢基地(青森県)、小松基地(石川県)の3基地に纏まった数の「航空機えん体」が設置されている。それ以外の、百里基地(茨城県)、築城基地(福岡県)、新田原基地(宮崎県)、那覇基地(沖縄県)の4基地への設置はあまり進んでいない。 陸上自衛隊では掩体壕や塹壕を構築するため掩体掘削機を配備している。
この機体も日本語版wikiにはありません。『ヒコーキの心」の中にも、リヒトホーフェンの撃墜数の項に「第6位 ソッピース1½ 支柱複座戦闘偵察機」と出てくるだけです。 【試作機の資料も充実していて、とても参考になる「WINGS of WWⅠ」というサイトでは、「1 1/2という変な名前は、翼間支柱が片側1本半というニックネームが定着してしまったということである」。う~ん。 【『第1次世界大戦の軍用機 写真特集』では「11/2ストラッターという名称は、上翼と下翼の間の「支柱(ストラト)が1本半」という意味だとされるが、支柱はたくさんあり、どの部分を指して「1本半」だとしているのかは不明(原文ママ)」。投げてる⁉ 【英語版wikiには2つ出てきます。 「上部翼を支える長い支柱と短い支柱から、1+1⁄2 ストラッターという名前が付けられた(意訳)」最初のと同じですが、長・中・短(片側2組)ありますよね・・。 もう一つは「1 対の短い (半分の) 支柱と 1 対の長い支柱によって胴体に接続され、正面から見ると「W」を形成。これにより一般的な愛称である1½ ストラッターが生まれた」と。ソレっぽいです。 う~ん、難解なネーミングセンス・・。さすが英国