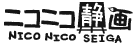主翼 形状 を含むイラストが 28 件見つかりました ( 1 - 20 件目を表示 ) タグで検索
マックスが乗ってたな 武器商人が歴代の歌い ちなみにΔの世界でも No.26311790 Δではク これあれやろ火力+10 2016夏modeの扶桑山城 クウォーターちゃん実 デュランダルが
おいらも好きでっせア ↑コスモウォーリアー こうしてヤマト色にし コイツが「二代目宇宙 ↑しかし【18代ヤマ 戦力と機能性を徹底追 色が違うだけで印象ガ アンテナ要らな
↑想像力が金で買えた ここまで来ると費用効 攻撃が可能であること ↑オスプレイ(V-22) 堅実な設計だから拡張 貴重な複座戦闘機。や 性能もひどいやろ…設 アルミ系合金は時
>メガ粒子砲を正面か キマイラ隊の旗艦もコ 近藤版じゃこのバカで こいつ推力で飛んでる リリー・マルレーンの 対艦用だとしてもあん 側面のぽっちってミサ ホワイトベー
スカイレーダーなら復 空母や艦艇に搭載され ↑×2やはりそうした方 ジェット 細か過ぎてごちゃごち 相変わらずの細やかさ
クラフティン共和国で採用された戦闘機。アルセイア連邦とのライセンス契約を結んだF-63B制空戦闘機[im4804875]をベースに、改良が加えられている。(作成者であるゆかほむさんに画像投稿の許可はあらかじめ取ってあります。) ベース機が既に旧式化していたため、生産を担当する東扶重工の手によって一部再設計されている。主な改修点は、主翼の改良・ミサイルマウント形状の見直し・コックピットのRS配線の見直しなど。 なお、ベース機ではTNTキャノンを搭載していたが、主翼形状などの形状変更により搭載できなくなってしまったため、オミットされている。その代わり、ミサイルの搭載量を増やしたり、連射式の機銃を装備している。 なお、本機をベースにしてステルス機、CF-05A/Bが開発された。 ←前im5003327 次→im5028378 twitterの方で開発状況などをつぶやいています。(基本不定期)https://twitter.com/max89457610 軍事部wikiの方でも活動しています。同盟国募集中です。http://www61.atwiki.jp/maikuragunzibu/pages/161.html
金属製主翼の設計を担当していただけあって、V・M・ペトリャコーフの応力外皮構造の設計は複雑ではあったが、優秀であった。双発の水冷式エンジンは綺麗にカバー内に収められて、ソ連流である主翼内に冷却水ラジエターを設ける構造だった。 さらに、このラジエターの冷却空気は主翼前縁からダクトを通って、主翼上面のシャッターの隙間から排出され、出力を増す事を意図していた。エンジンには過給機、可変プロペラを装備した。機内装置の全ては電気化され、これはアメリカの影響を受けたものだといわれている。 1939年、VI-100の試作機の一号機が初飛行を記録。高度10,000mで時速630kmを記録する。しかし、三座型の爆撃機仕様を量産に移すように命令が下る。理由は定かでないが、これは仮想敵国の中に高高度爆撃機を持ち合わせている国が無く、高高度戦闘機の開発が必要ないと判断されたためだといわれている。三座型の爆撃機型、PB-100は1940年に認可され、試作機が製造された。VI-100との違いはダイブブレーキ(急降下速度を減速させる)の追加、機体構造や主翼の形状変更など、多岐にわたる。過給機も取り外されてしまった。これが実戦に送り出され、1941年から始まった量産型は設計者であるV・M・ペトリャコーフを敬してPe-2と改称された。
「F-8 クルセーダー」はkfactory様、「航空兵器セット2」はカツオ武士様、「F-100 スーパーセイバー」はSketchUpのモデルさんです。F-100はミッキーだけに03?00だったり消えてたり。 【「最後のガンファイター」を爆装、戦闘爆撃機F-100が上空援護。岡部先生も指摘されてましたが(文庫版解説)、F-100が3,190 kgの所F-8は2,000 kgしか積めないですからね。907.2 kgのMk 84×2積んでみました。でも安定翼が2枚なので燃料タンクな気も。F-5の方は爆弾ぽく描いてあるので余計そう感じる?F-5の方はフィンの形状からB61核爆弾にも見える・・。F-5は3,175kg搭載可。胴体下に増槽があり、パイロンに1発ずつ懸架されているのでMk 83×4で。 【主翼を降り畳んだF-8とF-5の幅ですが・・そんなに変わらない気がしていたので並べてみました。
ロイヤル・エアクラフト・ファクトリー(The Royal Aircraft Factory)による「型番の“F.E.2”とは“Farman Experimental 2”の略で、同じく推進式の航空機を製作していたファルマン兄弟の機体を範にとったという意味を持ち、型番“B.E.”は“B lériot Experimental”の略で牽引式の機体ブレリオ XIに範をとった」という事になります。分かり易いというか義理堅いなという気もします。 【折角なのでSketchUpより、ブレリオ XIとファルマン複葉機をお借りして並べてみました。 【ブレリオ XIの画像・資料を検索すると、当時の写真、図面、複製、模型、イラスト等々で様々な形がヒットするので混乱します。単座複座はともかく、エンジン形式も主翼形状も複数あったりします。ドーバー海峡を横断した機体としたいので、単座で主翼は(凧の様な)たわみ翼、エンジンはアンザニ式 3気筒。
MiG-1からの改修点として、エンジンの変更に伴い補助燃料タンクを増設していること、キャノピー形状を変更して操縦席からの後方視界を向上させたこと、主翼の上反角を増やして機体安定性を向上させたぜ!
He111 Zは、2015年2月の『独兵器コレクション 08』でUPしたモデルさんを再度弄らせて頂きました。脚の追加や主翼形状の手直し含め、He111と共に全体を見直しています。 【RATOを8基ぶら下げました。Me321で、この組み合わせならⅢ号・Ⅳ号を載せて飛べると思います、思うのですが
ブロック社が開発した4座爆撃機MB200の 発展改良型として開発された機体。胴体はさほど形状に変化が無かったが、主翼は低翼配置に改められ(逆に水平尾翼 は若干高い位置に移動した)、主脚は引き込み脚となるなど近代的な改設計が施されている。 MB200の量産発注と前後して開発が始められ、1934年末に原型が初飛行した。MB200に比べ性能がアッ プしていたため、フランス政府は当機の量産を発注し36年から量産型の納入が開始された。量産はMB200同様に フランスの航空機メーカー各社で行われている(ブロック社が製造した機体はごく少数である)。 最盛期には12個の爆撃機部隊に配備された当機であったが、1930年代末には時代遅れであるとして順次新鋭機 への転換が行われることになった。しかし第二次大戦の勃発により転換は間に合わず、結局フランスが降伏するまで当 機は第一線で使用されることになってしまい、ドイツ軍との交戦で多大な損害を被ることになってしまった。 なお、ルーマニア空軍に輸出された機体(10機または24機説、45機説あり)もあるが、フランス本国の機体と 同様に侵攻したドイツ軍に接収され、ごく一部がドイツ軍の訓練任務などに再利用されている。
航空戦艦と言えば彗星。 【「運用は格納庫から昇降機で航空機作業甲板へ艦載機を揚げる所までは通常の日本空母と同一だが、艦載機をトロッコに載せ左右一基ずつの一式二号火薬式射出機に載せ射出(wiki)」。 【射出用の架台の底部には爪があり、カタパルトのシャトル?に引っ掛ける事で引っ張られる構造ですよね?トロッコはカタパルトにセットするまでの軌条を移動するための台車であり、カタパルトには機種毎に形状の異なる架台のみを人力でスライドさせてセットする事になるかと。 【トロッコ形状については次作にてとして、今回は架台の形状について。(自分的に)普通に考えて③の水平だとずっと考えてきましたが、斜めだったとのイラストを見つけビックリ。手書きでは1段(①)、模型では2段(④)だったり。爆弾積んで増槽も2本抱えて胴体後部で支えるのは重量的に持たないんじゃないかと主翼下に変更してみたのが②⑤。 【「航空戦艦日向からの初発艦」。実際に彗星で発艦された方の手記で、尾輪が格納式の機体であった事等参考になりました。斜め固定の記載は残念ながら…。写真が欲しいですねぇ