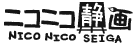安定性 を含むイラストが 193 件見つかりました ( 121 - 140 件目を表示 ) タグで検索
(れいしきかんじょうせんとうき: 以下、零戦)は、大日本帝国海軍(以下、海軍)の主力戦闘機。皇紀2600(西暦1940)年に制式採用され、末尾の00で「零式」の型式が付いた。(九六艦上戦闘機は皇紀2596年採用のため末尾の96を取って九六式)海軍の艦上戦闘機(以下、艦戦)としては実質的な最終型式で、支那事変の半ばから大東亜戦争(太平洋戦争)の終わりまで各地で活躍したことで知られる。大東亜戦争初期に連合国の戦闘機を駆逐したことから、主交戦国のアメリカ軍から「ゼロファイター」(コードネーム「Zeke」)の名で恐れられた。 このゲームではCFS2と異なり、vulnerableオプションの設定に関わらず零戦などの7.7ミリ機銃がかなり冷遇されており、グラマンなど防弾が施された機体には機関部やコクピットなど致命部にピンポイントで打ち込まないと手ごたえがほとんど無い。ほぼ無反動なので射撃安定性が高いのが救いだが、20ミリを極力使わない坂井三郎ごっこは無謀。
どうも、犬猿です。二足歩行戦車M1A3ベナティクス。左から基本形、近接戦型、重装型、狙撃戦型、式典用。 全体に脚部、椀部を強化。サバイバルモードでも、ちゃんと足からコクピットまで登れますし、注水、再装填等が可能。近接戦型は主砲銃身の短縮化、腹部に12連機銃。重装型は盾の強化。狙撃戦型は砲の弾頭ズレを防ぎ精度向上、腰部と脚部を五か所のピストンで固定し射撃時の安定性を確保(という設定)。式典用は武装はコクピット機銃のみ、盾とポールはピストンで脱着、腹部に防弾ガラス謁見席。
どうも!Gutenなんとか! 今回は最近開発したTNTキャノンについての解説です!とりあえずこのTNTキャノンの設定(御託です) 78年式四型対戦車砲(119mm92口径ライフル砲) この戦車砲は口径長を11000mmという長砲身にする事によって安定性を上げ 実際の砲口径の119mmではなく120mmの砲弾を使う事によりガスの噴出を少し少なくする事で高い貫徹力を付与した我が国の独自開発の砲です。 又、この砲は粘着榴弾が強力なので粘着榴弾の砲身寿命への影響の少なさがこの砲の短所の砲身寿命の短さをカバーし、その短所を相殺しています。 と、ごちゃごちゃ抜かしましたが要するに 「粘着榴弾がめっちゃつええぜ!!!d=(^o^)=b」 的な事が言いたい訳でありますwこの78年式四型対戦車砲はアイテム式の自動砲で大きさは5×5×5(砲隔壁を除く)とけっこう小さめに抑えた我が国の技術の結晶です!さて、こっからが本題ですがこの砲を今回輸出しようと思います(需要無いけど...)こんな産廃を欲しい!と言ってくれる方は私のPSNアカウントwasei-sinden迄お声掛け下さい!!基本的にはvitaの輸出ですが、PS3、PS4の方も画像で良ければ取り扱い説明文と共にお渡しします!と、まぁ今回はこんくらいで解説というか宣伝?を終わりたいと思います!最後になりましたが前回のブリキの軍事部クラフター兵器開発記 ( 1 )とブリキの軍事部クラフター兵器開発記 ( 番外編 )を拝読して下さった方々に最大限の感謝を申し上げます!これからもぼちぼち投稿させて頂きますのでこれからも宜しくお願いいたします!以上今回は終了です!ご拝読ありがとうございました!!
スピットファイアは英国を代表する戦闘機。34年に発行された要求仕様に基づき、ロールスロイス・マーリンエンジンを搭載する迎撃戦闘機として開発された。抵抗の小さい楕円翼の採用により、生産性は落ちたが高速と運動性を両立させることが出来た。また構造に工夫をこらしていたため、薄い翼にもかかわらず強度は高く、多数の機銃や機関砲を搭載できた。基本設計が優れていたため、エンジンをパワーアップしつつ終戦までイギリス空軍の主力戦闘機として使用され続けた。ただし2000馬力級のグリフォンエンジンを搭載した型は、強すぎるエンジンによる安定性不良に悩まされた。ドイツのBf 109と比べると、最高速度と旋回性能でやや勝り、急降下性能と高速での操縦性でやや劣ると言われる。また初期のマーリンエンジンにはマイナスGでエンジンが咳き込む癖があり、垂直面での戦いでは不利となった。一方で、航続距離が短く侵攻作戦に向かない、狭い主脚幅のため着陸が困難(プロペラが低い位置に来る、倒立エンジンのBf 109の方が深刻だった)といった共通する弱点も持っていた。
すくすく型水雷艇 2番艦「萃香」 兵装:対艦魚雷発射管×6 30㎝三連装砲×1 白沢で有効射程の短さが問題となり、主兵装がVLSから30㎝砲に変更され、大型の砲で敵を長距離から「殴る」ことを主体とし、砲艦と呼ぶべき艦艇となった。 反動軽減装置を砲塔内に多数設置することである程度の安定性を確保している。 ただし大口径砲故に散布界が広くなることが懸念されている他、重量増加により機動力が低下した。 一応ワークショップに上げておきました。→http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=783500205
高さ4.5マスに回転砲塔、砂弾装、全面水流装甲をねじ込むことに成功。弾頭と装薬は共に14発。とりあえずは目標達成。これも半没式のおかげであります。河村重工初の暴発しない半没式戦車。他にも多数開発したものの全て暴発。この戦車も元は暴発するタイプだったので飛距離を200→120まで落として安定性を確保することに(半没式なのに飛距離がないためタイトルに一応と記した)。飛距離に関しては改善の余地がある。 しかし幅7マスに高さ4.5マス、総ブロック数295にこれだけ機能を詰め込めれば十分だろう。それなりに満足している。
心綺楼が出ていた時期に合わせて描いていた「東方小型四駆」の宗教関係キャラのマシン。 二台目は白蓮のライバルと言える神子のマシン「フラッシュ・サーベル」です。 こちらも白蓮のマシンと同じく心綺楼での神子の特性に合わせて描いたものですので、深秘録以降に描いていたら相手に神子のマシンタイプ(直線orコーナー)の選択を迫る能力が備わっていたかも知れません。 白蓮のマシンと対になる様、直進安定性と最高速を重視した性能という設定にしました。 余談として、イラストに描かれている閃光は17本描かれています。(十七条のレーザーからとって) Pixiv投稿版:https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=49292663
完成したので晒す。 フレキシブルアームめっちゃ遊びやすい! 付属のインパクトエッジ/ナックルで両手塞がるのが勿体無かったので、ゾイドのジェノブレイカーをヒントに背中に装着。 ついでに重い背中武装を支えるために脚の後ろにもアンカー兼ホバーブースターを装備して安定性と機動力を確保 という設定。 おかげで片足立ちもギリギリ出来ます。 他の機体→clip/1735144
I-15に続いてポリカルポフ設計室が開発した、単葉・手動引き込み脚の戦闘機。 機体を可能な限り小型化することで高速性能を狙った設計だが、胴体が短く尾翼が重心に近すぎるため安定性は悪く、操縦には注意を必要とした。 初飛行は1933年で、34年から大量生産が開始されている。競争相手のスホーイの全金属製単葉引込脚付戦闘機I-14の方が数ヶ月前に初飛行したものの配備が遅れたためI-16の方が世界初の実用引込脚付戦闘機になった。I-15と共にスペイン市民戦争に送られ、戦争前半では優位に立っていたが、対抗のBf-109に武装(初期型は7.92mm×2のみ)以外で劣っており、後のLaGG-3、Yak-1、MiG-3の開発につながった。 その後中国やノモンハンで日本軍との戦いに使用され、96艦戦や97戦に対しては火力と防弾装甲により格闘戦に入らなければ互角に戦えたが、零戦との戦いでは惨敗した。 ドイツとの開戦時点では、一部の部隊が新型機に機種転換している最中であり、主力はいまだI-16であったため、緒戦で大損害を出すことになった。しかし初期の新型機に故障や不良品が多発したこともあり、頑丈なI-16はパイロットには信頼されていた。また、開戦当時は対地攻撃機のIl-2が少数しか配備されていなかったためI-15と共に対地攻撃機としても使用された。 特徴のあるシルエットから、敵からはアブ(日本)、モスカ(スペイン:蝿)、ラタ(ドイツ:鼠)などと呼ばれた。
スペースシップには特徴的なフェザリングモード(最高度からの落下時に、尾翼部分が回転し65°まで立てる事で降下スピードを抑え機体の過熱を防ぎ機体の安定性を保つ(wiki))があります。 【2014年10月31日の墜落事故は、07:19 母機から分離→07:29 ロケット点火→07:31 飛行速度マッハ1.02 フェザリング作動→07:34 空中分解。「加速段階の初期から減速時用のフェザリング・モードのロックを解除」「完璧な操縦から僅かでも外れると死に直結するという設計意識の甘さ」。その後の試験飛行は成功している様です。 【VSSユニティはこんな感じの塗装でしたが、Ⅲイマジンでは全面ギラギラに。しっかし、かっこ良く見える角度からの写真が多いですねぇ。斬新さ(異形感)のあった1と異なり、特に横や前からはビジネスジェットみたいで今一つアピール不足だから・・かな?
久しぶりに漫画を作りました 下手は変わりません... 今回は、スーパーGT300にフォーカス ラリーチューニングカーを走らせてみました フォーカスは、アメ車のメーカーのフォードが開発したハッチパックのFFスポーツカーです FFと言えども、スバルのインプレッサやスズキのスイフトとほぼ互角に並ぶ強さを持つ車で、当時のラリーは強敵でした 現在もモデルチェンジされて、その強さにも日々磨きが入っています しかし、ラリーと言う部分を理解していなければ、当然のことながらFFのスポーツカーと認識されがちです 悪路を走るラリーの世界では4輪ドリフトはスタンダード、つまり、4WDでラリーは基本なのです 4WDは、乗り心地までは考慮していないかもしれませんが、加速に対しては非常に安定性を持つ利点があります その分燃費は犠牲になるも、しっかりとした加速をさせてくれるのが4WDです しかし、システム自体も重く、曲がるとなるとアンダーステア傾向なのも4WDの特徴なのです FFやFRなどとは違う動きを見せてくれるのも、きっと4WDの特徴に含まれるかもしれませんね これからも作品をたくさん作るので、お楽しみに このお話はフィクション、あるいは二次創作です 実際の出来事とは、何にも関係ありません また、公道ではこのお話のような運転はせず、常に安全運転を心がけてください
竹型は初め、水上機母艦として計画されました。しかし、建造中に安定性が低い事や搭載機数の問題が出てきたため一回目の改装を実施、しかし間もなく電磁誘導式カタパルト(発着艦が可能なカタパルト)による小型艦載機の発艦試験が成功すると水上機母艦としての意味が無くなったため完成間近だったものを更に改装、現在の護衛空母の形になりました。この艦は旧日本海軍で言うところの千代田、千歳のような存在です。
「フォッカーの馬草」 【「フォッカーの懲罰」という言葉と主役のアインデッカーは知っていても犠牲となった機体は知りませんでした。他には「ル・グラン」コードロン G.4とブリストル スカウトくらい? 【今回困ったのは型式豊富、資料豊富のため何を作っているのかわからなくなる事でした。今回のは多分RAF 1aエンジン搭載BE2cになると思います・・。 【Royal Aircraft Factory B.E.2。「英の複座複葉偵察機」であり「英軍は頑なにB.E.2シリーズに固執し続け、再び血の4月で犠牲を重ねた(wiki)」との事。「用途が砲兵の観測と撮影」→「パイロットに割り当て」→「飛行制御に常に注意を払う事無い様に」→「制御より安定性」→「迅速な操作が困難」。致し方ないか・・ 【「パイロットが後席で偵察員が前席に座るため、後方へ旋回機銃が有効に使用出来なかった」が「なぜか最後まで改善されなかった」。ナゼソウスルノカ?英は更に進む(続
Bf110の後継機として開発された機体。DB605エンジン搭載の高性能駆逐機を目指していたが、空軍当局よりリモコン機銃、爆弾倉、急降下爆撃能力など過大な要求が出され、試作機は安定性に重大な問題をもっていた。しかしBf110の旧式化が目に見えていたため生産が強行され前線での事故が多発、すぐに使用禁止となった。全面的な改修によりこれらの不具合は改善されたが、メッサーシュミット社では更に設計変更を加えたMe410の生産に入っていたため、Me210はハンガリーで生産されることになった。