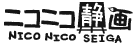金属製 を含むイラストが 160 件見つかりました ( 121 - 140 件目を表示 ) タグで検索
ポリカルポフ設計局がI-16の 強化改良型として星形複列エンジンを搭載する機体を設計、1938年に試作機I-180が完成しました。 I-180の原型は1938年12月15日に初飛行。機体は最初全金属製を考えたが、金属加工のノウハウがなくもI-16に類似した胴体は半モノコック構造の合板製、主翼はジュラルミン製となりました。空冷星形14気筒エンジンを取り付け12.7ミリと7.62ミリ機銃を2挺ずつ装備。6機が造られたが、空冷星形18気筒エンジンを装備したI-185のほうが有望と判断され、生産に入らなかった。I-185は木金混合製、原型は1941年1月11日に初飛行。しかし装着を予定していたエンジンの生産が遅れ、機体の生産工場が見つからずも開発は中止されました。
フランスのロワール社は1932年に全金属製応力外皮構造でガル翼式の高翼単葉の単座戦闘機ロワール 32原型を完成させた。フランス航空省は同時期に行った単座戦闘機競作に対して搭載エンジンを指定し たため、同機も他社の機体同様にイスパノスイザ社製エンジンを搭載していた。この原型機は翌33年1月 に墜落して喪われたが、この時には既にエンジンをグノーム・ローヌ社製星形エンジンに変更した発展型と なるロワール45原型機が完成していた。 ロワール社ではロワール45原型機のエンジンを強力なものに換装して時速370キロメートルを発揮さ せたため、同社はこの機体の設計をさらに改良し、34年夏にロワール46原型機を完成させた。この機 体に目をつけたフランス航空省は60機の量産型を発注し、これら量産型にはフランス空軍戦闘機として初 の無線機搭載も行われることになった。 1936年にスペインで内乱が勃発すると、フランス政府は秘密裏に少数のロワール46量産型(生産2〜 6号機の5機)を共和国政府軍へ引き渡したが、2機は短期間のうちに事故で喪われ、もう2機が戦闘で喪わ れてしまっている。フランス空軍への量産型納入は36年11月から始まり、翌37年には第6飛行連隊に 所属する4個飛行隊すべてが当機へ機種転換を完了した。 第二次大戦勃発直前の39年3月になって、すでに旧式化したとの理由から全機が飛行学校や射撃学校へ 移管され、第一線任務から順次退くことになったのだが、ドイツ軍が侵攻した時点でまだ1個飛行体が当機を装 備している状況であった。しかし、ドイツ軍の侵攻を抑えるには非力であったのか、目立った戦果は残され ていない。
複葉戦闘機として世界最後の機体。実用化時、既に時代は全金属製低翼単葉引込脚へと移っていた。開戦時には王国空軍戦闘機の約半数近くを占めていた。大戦後期には夜戦としても運用された。生産数はイタリア戦闘機最大の1781機。(設計:Celestino Rosatelli) アメリカやイギリスから新型戦闘機を入手できず、グラディエーターを主力としていたスウェーデンは、国産戦闘機完成までの間に合わせに本機を輸入している。
1936年にフランスの航空機メーカー各社が軍事産業の国有化の一環として国有航空機工業に吸 収された際に、ブロック社の技術陣はお蔵入りになっていた16人乗りの旅客機M.B.160の設 計案をSNCASO(国立南西航空機製造社:Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest)に 持ち込んでいた。この設計案を元に2種類の派生型を開発することとなり、旅客輸送機型のM.B. 161と爆撃機型のM.B.162の開発が同時進行で進められた。 旅客機型原型M.B.161.01は1939年9月に初飛行し、エール・フランス航空から発注 を得たが、その後フランスがドイツに占領されるとフランス工業界はサボタージュを行ったため、そ の影響から生産1号機が納入されたのは終戦後の1945年9月となった。 旅客機型の開発が優先されたため、爆撃機型M.B.162原型の製作は遅れていたが、1940 年6月にようやく初飛行することができた。片持ち低翼単葉、全金属製構造を持つ4発の重爆撃機は 長大な航続距離と大きな搭載能力を持ち、アメリカの B-17などに勝るとも劣らない 性能を示したが、1機だけ完成した原型はドイツ軍に接収されてしまい量産されることは無かった。 ドイツ軍に接収された原型機は、フォッケウルフ社の監督の下で各種のテストが行われ、1943 年からは長距離の秘密任務に従事していたのだが、終戦時スクラップにされてしまったらしい。
1932年に設立された民間向け小型機を扱うビーチ・エアクラフト社は現在では押しも押されもせぬ 小型機の代名詞となっているが、この最初の双発機を開発したときは、あまり売れるとは思っていなかっ たらしい。 全金属製・軽合金構造のセミモノコック胴体を持ち単葉双発のオーソドックスな6〜8座の座席を有す る機体(ビーチ・モデル18。愛称はツイン・ビーチ)は1937年に初飛行したが、おおかたの予想ど おり最初の生産機はほとんど売れなかった。19 40年になって米陸軍航空隊が幹部輸送機として20機を発注したことが切っ掛けとなり、また第二次大 戦の勃発による一般輸送用や航法・爆撃練習機などとしての需要が一気に高まったこともあって、かなり の数の機体が米陸軍や海軍に供給され、一部は武器供与法により英国へも配備された。また中国は輸入し た当機を軽爆撃機として使用している。 大戦終結後も米軍は当機を使用し続けており、米空軍は1960年代初頭、米海軍も1970年代まで 当機を輸送や連絡任務に使用していた。また世界各国へ輸出された機体(最後の機体は1970年に製作 された)も、結構長い間軍用や民間機として活躍している。
後に優秀な飛行艇だと評価されることになるPBY飛行艇 の原型機XP3Y-1が初飛行した直後に、PBYよりも大型の海洋哨戒爆撃機として開発計画が 立ち上がった機体。 米海軍はコンソリデーテッド社とシコルスキー社の2社に対して審査用の原型機製作を発注し、 1937年に両社は審査用機体を初飛行させた。シコルスキー社の機体XPBS-1は数々の新機 軸を盛り込んだ画期的な機体だったが、後から審査されたコンソリデーテッド社のXPB2Y-1 の方が、幾つか欠点があるもののシコルスキー社の機体より量産に適すると評価された。 米海軍は即座に制式採用を行い機体を調達するだけの予算を確保していなかったため、コンソリ デーテッド社は審査の際に発見された欠陥を修正する機会に恵まれた。特に安定性の問題が酷かっ た垂直尾翼は試行錯誤のすえにB-24のような 双垂直尾翼に変更されている。 1939年に制式採用となり翌40年から部隊配備が始まったが、第二次大戦開戦により量産型 の発注数は増加し、一部の機体は英国海軍へ供与されている。全金属製の機体に大きな高翼配置の 主翼を持ち、主翼両端には引き込み式の安定フロートが装備されている。爆弾倉は厚い主翼内部に 設けられていた。
ビッカース ヴァレッタ(Vickers Valetta)は、1940年代終わりの英国の双発軍用輸送機である。本機は引き込み可能な尾輪式の降着装置を備える全金属製の中翼単葉機であった。
LeO 451は、フランスのリオレ・エ・オリビエ社(Lioré et Olivier)によって第二次世界大戦直前に開発された爆撃機である。1937年1月16日に原型のLeO 45-01が初飛行したが、この機体をより強力なノーム・ローンエンジンに換装したのがLeO 451で、1号機は1938年10月21日に進空した。全金属製の機体で、胴体を曲線でまとめた双尾翼式。1939年9月から量産開始したが生産が遅れ、ドイツ軍侵攻時にはわずか100機程が使用可能状態だったに過ぎなかった。このため、優れた爆撃機でありながら、実際の戦闘において貢献することはほとんど無いまま終わった。 停戦後も生産は続けられ、様々なバリエーションが作られた。最後の機体が退役したのは1957年であった。
海軍制式機としては最初の全金属製低翼単葉機となった。設計当時、戦闘機を中心に主流となっていた張り線を使用した薄翼を採らず、高速時の空気抵抗減少のために張り線の無い厚翼を採用した。主翼外形は曲線を繋いだ楕円翼とした。また、国産実用機として初めてフラップを採用しているぜ!
初めての人ははじめまして、見たことある人はお久しぶりです。 ミスターAWさん主催のMMDカーモデラー改造祭に参加のため、 Sタイヤと金属製エアバルブ配布です。 タイヤは溝や裏側まで作ってありますし、エアバルブもキャップを外した中まで作ってあります(簡易ですが)。 ちなみにモーフでタイヤが摩耗します(笑)。 何気に完全自作モデルは今回が初・・・といっても パーツだけなんですけど(汗)。 https://bowlroll.net/file/252485 にて配布中です。 パスワードのヒント『今回配布されたタイヤの類別は?』 PR画像に写っている車両は、 https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im6841500 で紹介しています。 2021/4/23:Ver1.00 2021/4/24:Ver1.01 モデル組み込みの際、 タイヤ摩耗モーフの頂点移動がずれ込むため、 タイヤを90度回転し、頂点モーフを再設定しました。
ユンカースお得意の鋼管構造とジュラルミン波板による機体構造は軽い割に強度が保てますが、抵抗が大きくスピード面で不利でした。1930年代後半には旧式化しました。そこでJu 52の後継機として開発されたのがJu352です。アルミなど戦略物資を使用しない思想で全金属製から鋼管構造に合板と羽布張りの胴体、木製主翼の木金混合で、プロペラまでも木製(逆ピッチ可能)へと変更しました。しかし結果的には変更による重量増加により他国の輸送機に比べ性能的に劣っており、また戦況から戦闘機優先の生産の命令が出されたこともあり、生産数は50機どまりとなりました。ヘルクレスは、独語で「ヘラクレス」の意味。
アラドAr 96は第二次世界大戦時のドイツの高等練習機である。全金属製の単葉単発機で、密閉式のコックピットと引き込み脚を有する近代的な機体だった。1938年に初飛行した。 生産は前期型はAGO社で、後期型はチェコのレトフ社とアヴィア社で行われ、戦後もC-2という名称で数年間続けられた。合計1万1,000機以上製造されている。また、ハンガリーでも少数ではあるがライセンス生産された。
大まか過ぎるし分かりにくいが、打刀の変遷を紹介する 昔、刀といえば短刀のようなものをさした 腰刀(短刀)が長大化し、それまでの平造りの短刀から鎬造りの脇差や刀に変化し、太刀の指添えとして用いられたそれは 下級の兵士や庶民の差料として好まれ、次第に製作も携帯方法も面倒な太刀から取って代わった 上段 平安時代から平造りの長めの刀はあったとされ残存していないが、南北朝期の春日大社の打刀のような感じだったと想像できる 腰刀の形式は画像の合口形のほかに呑口形などがあるが、金具部品の分かりやすさから赤木柄腰刀をモチーフとした 南北朝時代の品 中段 黒漆合口打刀。粗末なものが多く、庶民が使用する消耗品であったことから残存数が少ない(博物館に展示されているものは 一級品が多い)。糸巻きは角製の柄頭に掛け止めが多い。無論同形式の高級品もある。先反り二尺程の片手打ちの刀が入る 大体鍔がないか、小鍔が入る 室町前期、ないし中期から後期に流行(末備前、末関、末相州等各地) 下段 黒漆打刀。天正拵として知られる。二尺三寸以上になり太刀と変わらぬ長さを持つ。鍔も付き始めるが一般的なのは安土桃山時代から だとされる。助真拵や江雪左文字などが有名であるが、室町時代を過ぎると後の肥後拵に似る圧切長谷部など、金属製の柄頭の 孔の中に柄糸を通す形式が増えだす。平安以来の太刀は打刀に改造するため磨り上げ(短くする)が行われ、無銘になることが多い磨り上げ (天正磨り上げという)。また、それを写した豪壮で反りの浅い慶長新刀がこの時代の代表となる(堀川国広等) ※間違っていることがあったらコメントで教えてくれるとありがたいです
ツポレフ I-4はソビエト連邦の複葉単座戦闘機である。1927年、ツポレフ設計局においてパーヴェル・スホーイが初の設計を行った機体と考えられている。I-4はソビエト連邦初の全金属製戦闘機であった。
くるくるカールがよく似合うエルフ(女)には、遊び毛がいっぱいあるふわふわのボリュームたっぷりポニーテールを♪ 髪留めは、冒険者らしくクセのない金属製デザインでお願いします。
https://lenasfactory.wordpress.com/%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E7%89%A9/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%ABmmd%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB/ Twitterを見て即興で作ったハンドパンっぽいものです。 色はスフィアのみ。お好みでスキに改造してください。 ボーンはセンターと蓋のみです。
HFB320 ハンザジェット(HFB-320 Hansa Jet)は、1964年から1973年にドイツの航空機メーカーのハンブルガー・フルクツォイクバウで生産された全金属製、双発の10座ビジネスジェットである。
1932年にフランス航空省が出した新型夜間爆撃機の仕様書に基づいて開発された機体。両大戦の 狭間となる平和な時代(かつ全世界的に不景気な時代)だったため、航空機メーカー各社は数少ない軍 との契約にからむチャンスだとして積極的にこの仕様書へ応え、5社から設計案が提出されることとな った。 ブロック社の提出した設計は全金属製の固定脚高翼単葉双発機で、同時期に英国で開発された ブリストル・ボンベイや ハンドリ・ページ・ハローなどに似た 4座機であった。 審査の結果、ブロック社の案とファルマン社の案(F221) が採用され、33年に量産が開始された(量産型発注は34年とする説もある)。原型機は設計から推定され る最高速度よりも低い能力しか発揮できなかったが、量産型では信頼性の高いエンジンと、秀でた部分も無い かわりに特に欠点も見あたらない無難な機体であると評価され、最終的に200機以上がフランス空軍へ供給 された。また大型機開発の経験がなかったチェコスロバキアにおいても、当機のライセンス生産が行われている。 第二次大戦が勃発した時点では、フランス空軍の機体は全機が訓練用として格下げされていたが、チェコス ロバキア空軍の機体は第一線の部隊に配備されていた。ドイツ軍の侵攻によりこれらフランス・チェコスロバ キアの機体は鹵獲され、ドイツ空軍の乗員訓練やグライダー曳航、一般貨物輸送などに流用されている。なお、 少数の機体はドイツからブルガリア空軍へ供与されている。