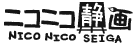1943 を含むイラストが 208 件見つかりました ( 161 - 180 件目を表示 ) タグで検索
大祖国戦争序盤において、これまでの53-K 45mm対戦車砲がドイツ国防軍のIII号戦車やIV号戦車にかろうじて対抗可能であったという状況から、赤軍は1942年に改良型の45mm対戦車砲であるM-42対戦車砲を開発した。 基本構造はこれまでの53-K対戦車砲と同一であるが、初速(760m/sから870m/sへ)向上のために装薬を増量し砲身が延長され、重量増加を抑えるために防盾が薄くなっている。大量生産のための簡素化も行われている。1943年には部隊配備が開始されたが、ドイツ軍の新型戦車であるパンター中戦車やティーガー重戦車の正面装甲を撃ち抜くことはできなかったため、待ち伏せでIV号戦車やパンターの側面を狙うようになり、榴弾や散弾を発射しての対人戦闘に従事することも多かった。 終戦後の1945年中ごろには生産が終了した。
1937年に中止された「ウラル爆撃機」計画に続いてドイツ空軍省は戦争用強力爆撃機である 「爆撃機A」計画を提言した。計画された性能は当時の技術力では現実の難しいものであり、しか も急降下爆撃能力までも求められていたため、開発はさらに困難なものとなっていた。 この開発を委任されたのがハインケル社で、同社の設計者ギュンター兄弟は飛行性能を高めるた めにあらゆる新機軸を盛り込んだ設計書を当局へ提出した。特に軍が要求した性能を満たすために 必要であった大馬力エンジンについては当時の量産エンジンでは出力不足であったため2基のDB 601エンジンを結合したDB606(2,500hp)を使用することにした。 He177と形式名称を与えられた機体は1939年に完成したが、エンジン冷却法の未完成や 急降下爆撃に耐えるための機体補強などで極端に重量増加した機体は、設計値をかなり下回る飛行 性能しか示さなかった。しかもエンジン加熱による出火など極めて危険な要素を含んでおり、生産 前機として製作された35機のうち25機が事故で失われるほどであった。 それでもHe177は軍に制式採用され、その後も改良が進められ1943年からDB610系 列エンジン(DB605を結合)を搭載したA-5型が生産されるようになって、初めて使い物に なる機体が軍へ納入されるようになったのである(ただしエンジン過熱や稼働率の問題は最後まで つきまとった)。 A-5型からは「グライフ」(頭が鷲、体がライオンの空想上の動物。グリフォン)と正式な呼 称がつけられゲーリング元帥の『自慢の翼』となったが、ドイツが制空権を失いつつあったこの時 期では敵に与える損害よりも受ける被害の方が大きく、電撃戦の再来を望むべくもなかったのであ る。 なお、A-5型には「フリッツX」やHs293などの誘導爆弾を搭載できる機体や空対空ロケ ットを多数装備した「対爆撃機用爆撃機」などの派生型も多数存在した。
宮史郎(1943.1.17 - 2012.11.19) ぴんから兄弟 若い人はノブ&フッキーのものまねでしか知らないだろうな。自分はリアルタイムで観ておりました。
Wikipediaの時雨の項目にある1943年の時雨と五月雨とされる写真、あれ多分間違いじゃないですかね?同じ写真で駆逐隊番号が読めるやつがあって、そっちには戦前の白露と時雨と書いてあるんですよ。つまりあれはさみしぐではなくしらしぐ(早口)
戦艦もお借りした。 お借りしたもの。Su-35・スカイドーム(ぴくちぃ様) モブ駆逐艦1945・モブ航空母艦1941・モブ高速戦艦1940(改装)・モブ巡洋戦艦1943(改装)・モブ超弩級戦艦1943(Tansoku102cm様) HgSSAO.fx ver0.0.3・PowerDOF.fx v0.0.5(針金P様)MikuMikuEffect用ディフュージョンフィルタ・AutoLuminous Ver.4.2(そぼろ様) 雲エフェクト(ラテ様) 水面エフェクトver5.0(ビームマンP様)
第二次大戦中の1943年に英国ブラバゾン卿(英国航空大臣兼運輸大臣(当時):John Theodore Cuthbert Moore-Brabazon, 1st Baron Brabazon of Tara)は、 戦争終結後の平時に大型旅客機市場で必要とされる航空機の研究・提言のための委員会を設立した。 委員会では海外航路用の長距離大型機から支線航路用の短距離機までの4タイプ(後に5タイプに 増えた)のレポートを発表、英国内の航空機メーカーはこのレポートに基づいて、民間輸送用の機 体開発を行った(1944年に軍需省が各タイプの航空機仕様書を発行したため、正規の開発契約 であった)。 デ・ハビランド社も幾つかの機体を開発したが、そのうち支線路線用(仕様書26/43)とし て開発されたのがDH104のナンバーを持つ機体で、原型機は終戦直後の45年9月25日(偶 然にもデ・ハビランド社創立25周年記念日であった)に初飛行し『ダブ』(Dove:鳩の意)の愛 称が与えられた。8〜11席の客席を持つ初期生産型は英国内よりも海外の航空会社へ売れたが、 その後に発売された6席のVIP輸送機は国内外の企業経営者に対して好感触を得て、ビジネス機 市場の一角を占めるに至った。また仕様書C13/46に適合する軍用連絡通信機としてのモデル も開発され、英空軍および英海軍に採用が行われた。この軍用型は『デヴォン』(Devon:地名)と 名付けられた。 デ・ハビランド社は『ダブ』の成功を受け、より大型の4発機市場(DH86 の後継機)に対応した改良型を開発することにし、1950年5月に機体を拡大した4発機DH11 4(後に『ヘロン』(Heron:鷺の意)の愛称を与えられた)原型の初飛行に成功した。4発機型も 国内外の航空会社に対してセールスに成功したが、軍用型としても英空軍女王飛行小隊[Queen's Flight]の VIP輸送機や英海軍の連絡輸送機として採用が行われている。
1943年8月22日より、「時雨」「浜風」「磯風」「漣」は第七聯合特別陸戦隊に従事するが、米軍機の妨害により失敗した。8月25日からの第2次作戦では、駆逐艦「松風」を陽動部隊とした他、同編成で輸送作戦を再開、レカタ到着後陸戦隊の収容に成功する。続いて8月30日から9月1日にかけて、「松風」「磯風」と共同し三次にわたるツルブ輸送作戦に従事する。その後、「時雨」は10日ほどラバウルに停泊して訓練に従事した。9月20日~21日、ラバウル~ブカ島輸送任務に従事。10月1日附をもって第2駆逐隊「五月雨」が第27駆逐隊に編入された。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E9%9B%A8_(%E7%99%BD%E9%9C%B2%E5%9E%8B%E9%A7%86%E9%80%90%E8%89%A6)動画sm24924819に使用した静画。時雨視点として、同じ場所でカメラを間逆にして撮ったもの。この頃は、同じ小隊でもばらばらに行動してたりして、この4人が揃って行動したことがどれほどあったのか、良く分からない。作った艦これ動画mylist/42341820ツイッター https://twitter.com/Me_Myafky
第二次世界大戦初期のイギリスの主力双発爆撃機の一つ。細い金属フレームを斜め格子状に組み合わせて編んだ上に羽布を張った大圏構造を採用し、生産性は悪かったが軽量かつ被弾に強かった。 原型機は1936年初飛行、量産1号機が1937年初飛行、1938年から実戦部隊への配備が開始され、初の実戦参加は1939年9月。開戦時はドイツへの昼間爆撃にも用いられていたが、同年末の作戦中に甚大な被害を受けたことから夜間爆撃のみに用いられることとなり、1943年夏まではドイツやイタリア工業地帯への爆撃任務のほか地中海・アフリカ方面でも活躍した。これ以降は夜間爆撃でも四発爆撃機が主力となり、沿岸哨戒や輸送・爆撃練習・無線航法練習など様々な用途に転用された。水上航行中のドイツ軍潜水艦(Uボート)捜索のために海上を照らすサーチライトを主翼下に備えた機体や水上捜索レーダーを備えた機体、潜水艦攻撃手段としてロケット弾懸架レールを主翼下に用意した機体などが哨戒用に新たに生産された。これらを含め、イギリス爆撃機としては最多の11,461機が生産された。 「ウィンピー」(Wimpy)の愛称で親しまれ、また小説『ブラッカムの爆撃機』の題材にもなった。
タイトル通り、イギリス海軍イラストリアス級空母ヴィクトリアス(HMS Victorious 1943)を建造してみました。これまでで一番建造に時間がかかった。もう空母ヤダ。
1936年にフランスの航空機メーカー各社が軍事産業の国有化の一環として国有航空機工業に吸 収された際に、ブロック社の技術陣はお蔵入りになっていた16人乗りの旅客機M.B.160の設 計案をSNCASO(国立南西航空機製造社:Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest)に 持ち込んでいた。この設計案を元に2種類の派生型を開発することとなり、旅客輸送機型のM.B. 161と爆撃機型のM.B.162の開発が同時進行で進められた。 旅客機型原型M.B.161.01は1939年9月に初飛行し、エール・フランス航空から発注 を得たが、その後フランスがドイツに占領されるとフランス工業界はサボタージュを行ったため、そ の影響から生産1号機が納入されたのは終戦後の1945年9月となった。 旅客機型の開発が優先されたため、爆撃機型M.B.162原型の製作は遅れていたが、1940 年6月にようやく初飛行することができた。片持ち低翼単葉、全金属製構造を持つ4発の重爆撃機は 長大な航続距離と大きな搭載能力を持ち、アメリカの B-17などに勝るとも劣らない 性能を示したが、1機だけ完成した原型はドイツ軍に接収されてしまい量産されることは無かった。 ドイツ軍に接収された原型機は、フォッケウルフ社の監督の下で各種のテストが行われ、1943 年からは長距離の秘密任務に従事していたのだが、終戦時スクラップにされてしまったらしい。
エセックス級航空母艦。「飛行甲板以外にも、格納庫から横向きに直接射出できるよう舷側カタパルトも装備された。こちらは軽量な小型機だけに対応し、非使用時には上側に跳ね上げて格納する形式であった。しかし運用上メリットが少なく、1943年中盤には全ての艦から撤去された(wiki)」。 【舷側カタパルト。格納庫内からの発艦なのでもはや合成風力なんてモノは関係無し。英・独海軍には直角埋め込み型のカタパルトがありますがウォーラスやアラドであり、アベンジャーでは無いですからモノが違うかな。文中には「軽量な小型機だけ」となってますが、検索でヒットするのはF6FとTBFばかり。運用試験であり、魚雷は積んでないのでしょうけどね?空虚重量でも約4.8t…。合成風力無しで飛ばせるんですねぇ・・。次はアサシンP様まりりん様の加賀さんのカタパルトを
グラマン社において、ジェット戦闘機の開発は1943年から開始されており、1946年4月には双発複座のG-75案がXF9F-1としてアメリカ海軍から発注されている。これは1946年12月に単発単座のG-79案に発展したため、XF9F-1はキャンセルとなり、G-79案をXF9F-2として開発が続行された。XF9F-2は3機が製作され、1947年11月21日に初飛行している。XF9F-2は量産化が決定され、F9F-2として1949年から配備が開始された。 パンサーは朝鮮戦争に投入されたが、直線翼で構成された機体デザインは、ジェット戦闘機としては明らかに古い設計思想に基づいたものであり、空力的な性能において同世代のライバル機より劣っていた。結果、戦闘機としてよりも、主に対地攻撃機の代用として運用される事となった。しかしながら、性能差を搭乗員の技量でカバーするなどしてMiG-15を含む多数の敵機を撃墜しており、朝鮮戦争を通じて戦闘で失われた64機のF9Fのうち、空中戦で撃墜されたものはたった1機のみであった。1950年11月9日には、米海軍のW.T.エイメン少佐がF9F-2でMiG-15を撃墜し、米海軍初のジェット機撃墜を成し遂げている。朝鮮戦争休戦後は、改良型のクーガーと交代する形で第一線を退き、主に無人標的機として使用された。 アルゼンチン海軍は、1957年に中古のF9F-2を24機、加えて1962年に新品のTF-9Jを2機購入し2個飛行隊を編成、南米の海軍で初めてのジェット機部隊となった。
イムヤ:電ちゃんはともかく、なんでゴーヤが追いつけるのよ! ゴーヤ:獲物がいる限り、(航行能力の)限界を超えれるんでち!さっさと借金返せガジェ中のオンボロ艦! (イムヤ1933年進水 ゴーヤ1943年進水 はち1936年 いく1939年 しおい1944年 Uちゃ1941年 まるゆ1943年) 電:扶桑さんに聞いたのDEATH、いまの調子で借りると一生かかっても返しきれないくらいの額になるらしいですね…スキャンプさんのかわりに雷撃してやるのです。 イムヤ:ていうかここ陸上、しかも山の中!! Q(通報艦宮古):うちのイムヤの借金額は?A(標的艦摂津):8桁突入したばっかり 背景撮影地:長野県木曽郡木曽町(旧開田村) 国道361号線 新地蔵トンネル抜けたあたり ※車内から撮影MMD艦これ関係まとめ→clip/1522630
次:im10821636 前:im10810939 1945年(昭和20年)4月に天一号作戦の一環として、また菊水作戦と呼応して出撃した第一遊撃部隊所属駆逐艦、「朝霜」の最期のイメージです 単艦戦闘で生存者もいないため沈没前後の詳細は不明ながら、米軍が撮影した朝霜の最期と思われる写真では 三基の主砲は左舷側を指向し、最期の瞬間までその任を全うしたものと推定されます 司令:速力は変わらず12ノットが限度か? 艦長:はい。やはり敵も復旧までは待ってくれませんでしたな 司令:しかし駆逐艦一隻に戦爆連合数十機とは贅沢だな 艦長:ですな。その分、本隊への攻撃機が減ってくれると思いましょう 4/7の朝霜の行動 06:57 朝霜(第21駆逐隊司令座乗)が機関故障のため随伴不能となり艦隊より落伍 艦隊速力18ノットに対し12ノットしか出せず徐々に落後 11:00 機関故障のため隊列から落伍していた「朝霜」が視界外へ消失 12:10 落伍した朝霜より「ワレ敵機ト交戦中」との無電が入る 12:21 朝霜より「九十度方向ヨリ敵機三十数機ヲ探知ス」との無電連絡が入る。この後、同艦は消息不明となる この他、第二水雷戦隊戦闘詳報には「冬月三〇度方向ニ朝霜交戦中ラシキ砲煙ヲ認ム」と記録されていたそうです 〇お借りしたもの 夕雲型駆逐艦:im3973377 モブ艦載機・兵装1943セット:im6201664 寒い午後 TQ8:im6479979 エコノミースレイヤー霊夢-東方弾幕エンジン:sm26930387 【MMD】砲撃とか水柱とかビームとかビームとか:sm23871006
前:im10854776 1945年4月7日、制空海権が無い絶望的な状況下、大和を旗艦とする日本海軍第一遊撃部隊は沖縄救援に向け出撃。坊ノ岬沖にて米機動部隊の約400機からなる空襲を受け、これを敢然と迎え撃ちますが最終的に大和を含む6隻が沈没。大和の喪失は洋上航行中の戦艦が航空攻撃のみで撃沈された最後の事例となりました。 〇お借りしたもの 戦艦大和:im2876301 夕雲型駆逐艦:im3973377 モブ船演出セットIII:im5391224 モブ艦載機・兵装1943セット:im6201664 カーチスSB2Cヘルダイバー:sm27722273 寒い午後:im6479979 MME:sm26930387 sm23871006