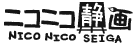1945年 を含むイラストが 229 件見つかりました ( 181 - 200 件目を表示 ) タグで検索
カス子キャラ、T3Dモデルさんと共にアサシンP様モシンナガンさん、nail様(BTA様)難民マントさんを使わせて頂きました。ありがとうございます。 【ローザ・シャーニナさんのイメージで。彼女は東部戦線兵士であり1945年1月に戦死となってしまいますが「戦闘中に肩を“狙撃”され負傷」というエピソードを頂いて、14ハクちゃんと撃ち合うシーンとか考えてたりします。
太平洋戦争を戦い、当時の艦隊型新鋭駆逐艦であった、朝潮型駆逐艦、陽炎型駆逐艦及びその改良型夕雲型駆逐艦、そして「島風」の計50隻の中で唯一終戦まで生き残った。日本海軍の駆逐艦は、激戦区に投入され非常に損耗率が高かったが、本艦は真珠湾攻撃から大和特攻まで16回以上の主要な作戦に参加し、戦果を上げつつほとんど無傷で終戦を迎え「奇跡の駆逐艦」と呼ばれた。(WIKIより) そんな駆逐艦を作ってみました。細部までは再現しきれてませんが、再現はしたつもりです・・・ この雪風の作成には模型サイトの画像などを使用していますので、現実の雪風とは少し違うかもしれません。 模型はタミヤ・アオシマ製の物を参考にしています。 この雪風は1945年頃の対空強化したモデルらしいです。 今更艦これ始めたの。ドロップするとイイネ! 2013/12/20/5:00 未完成形から完成形に画像を変換しました
主翼と胴体にミートボール、尾翼にストライプ入れてみました。 【ヒジョ~に頂点数の多いモデルさん。今回改めて集計してみたら合計2,166,284頂点。銃座が489,132頂点ありますからコレを他のモデルさんに交換するだけで随分軽く? 【珊瑚海後半・ミッドウェーと、ドーントレスと比べ一方的な被害担当役であり97式艦攻に劣る性能であった事は否めませんが珊瑚海海戦緒戦に祥鳳へ魚雷7本を命中させたのはこの機体。1942年6月のミッドウェー海戦にはTBFへの機種変が既に始まっていたというのが何とも。天山の実戦投入は1943年12月の第6次ブーゲンビル島沖航空戦、まして流星は1945年ですもんねぇ・・
大祖国戦争序盤において、これまでの53-K 45mm対戦車砲がドイツ国防軍のIII号戦車やIV号戦車にかろうじて対抗可能であったという状況から、赤軍は1942年に改良型の45mm対戦車砲であるM-42対戦車砲を開発した。 基本構造はこれまでの53-K対戦車砲と同一であるが、初速(760m/sから870m/sへ)向上のために装薬を増量し砲身が延長され、重量増加を抑えるために防盾が薄くなっている。大量生産のための簡素化も行われている。1943年には部隊配備が開始されたが、ドイツ軍の新型戦車であるパンター中戦車やティーガー重戦車の正面装甲を撃ち抜くことはできなかったため、待ち伏せでIV号戦車やパンターの側面を狙うようになり、榴弾や散弾を発射しての対人戦闘に従事することも多かった。 終戦後の1945年中ごろには生産が終了した。
今度は空母葛城が空襲時に停泊していた地点の写真になります。天城と同じ三ツ子島に停泊しており、写真の矢印の物体ががおそらく係留時に接舷した所と思われる。天城では触れてなかったが、この三ツ子島は当時は海軍管轄の島となっていた。留置所になってたらしく、レイテで沈没した瑞鶴の生存者が一時的に留置されてた話がある。話をもどして、空母天城は、1945年3月の空襲で損傷し、この場所に疎開。その後、7月の空襲で甲板に損傷を受けるも、機関部等に損傷がなく戦後には復員船として活躍していた。それにしても、目の前で姉妹艦天城が横転した所を見たのは、さぞつらかったことだろう・・・ 艦娘の呉軍港空襲:clip/1592210 撮影場所:セブンイレブン安芸音戸渡子店付近から 住所:広島県呉市音戸町渡子
世界で唯一実戦使用されたロケット戦闘機。 ロケット推力機関であるヴァルター・システムを搭載した無尾翼形態の迎撃戦闘機であり驚異的な上昇力と速度、30㎜機関砲の破壊力による活躍が期待されたが航続距離が無いに等しい、離陸用ドリーにダンパーがなく着陸装置がスキッド(ソリ)のため離着陸に危険が伴う、ロケット噴射に耐える処理を施した滑走路でないと運用できない、目標の爆撃機との相対速度が速いため攻撃が難しいなどの軍用機としての悪条件が多く1945年4月にMe163を運用するJG400と同時にMe163の運用は停止した。 ヴァルター機関とは、高濃度の「過酸化水素」が分解する時に発生する水蒸気や酸素を利用する熱機関の総称。 ロケット推進利用の他にタービンを回して軸出力としても利用される。高速魚雷や高速Uボートでも有名。現在も改良され使われている。低温式ヴァルターロケットを用いたロケットベルトはロス五輪開会式のデモフライトで有名。 他の使用例として、V-1号の発射カタパルト、V-2号の燃料タービンポンプ、Me262のRATO(ロケット補助離陸装置)、高速魚雷や潜水艦の推進装置等がある。 Me163が使用している2液式-高温式ヴァルターロケットエンジンは、自重150kgで1.5tの最大推力を発生する。排気は1,900度もあり普通の滑走路での使用は難しかった。最大6分間の噴射が可能であった。 またT液(過酸化水素80%濃度)とC液(水メタノール系燃料20%濃度)の扱いが難しく、特に「高濃度過酸化水素」の有毒/金属腐食性でメンテナンス間隔が短かった。 離陸すれば数分で高度10,000mまで上昇するロケット迎撃機であったが、敵機との相対速度差が大きいため照準しずらく、着陸時は単なるグライダーで低速のため低空で待ち伏せ攻撃にあっていた。
アメリカ海兵隊専用モデルであり、正式名称は「PISTOL, CALBER .45, MEU(SOC)」(MEU=Marine Expedition Unit、海兵遠征隊)。 アメリカ軍の正式拳銃がM1911A1からM9に更新された際、海兵隊独自の特殊作戦部隊であるMEU(SOC)は、M1911A1型の継続装備を決定した。そのため、更新処分される1945年以前に生産・納入されたM1911A1の中から状態の良いフレームを抽出し、フレーム以外のほぼ全てのパーツを新規購入して海兵隊の工廠で組み立てたモデルである。この背景には、新規武器を調達するためには議会の承認を得る必要があり簡単に購入できないということで、銃本体(=フレーム)の修理部品の調達という名分で購入する必要があったという事情がある。 主な特徴として、固定のハイマウントサイト、アンビセーフティ、ビーバーテイル形グリップセーフティ、パックマイヤー社製ラバーグリップなどが搭載されている。市販はされていない官給品の改造モデルゆえ時期によりさまざまな仕様があるが、スプリングフィールド・アーモリー製スライドを使用しているのが確認されている。 海兵隊は実戦・訓練による消耗が激しいため、その後は供給不足を補うために次期正式拳銃の採用トライアルまでのつなぎという名目で、新規購入したスプリングフィールド・アーモリー製プロフェッショナルモデルをベースに、同様のカスタムを施したモデルを暫定調達している。
第二次大戦中に米国は対ドイツ戦の前進基地となりえる英国が失われたときのことを想定し、米国本 土から直接ドイツを爆撃できる大陸間爆撃機の要求書を発行した。当時は空中給油の技術が確立してい なかったため「4,500kgの爆弾を搭載して片道5,500kmの距離を無着陸で横断できる」能力が 必要とされたのである。 コンソリデーテッド社(コンベア社の前身)が提案したモデル37は、同社の B-24に似た 2枚の垂直尾翼を持ち、6基の空冷エンジンを推進式に配置した珍しいスタイルをしていた。この提案 が米国陸軍に採用され、設計変更(垂直尾翼は1枚となった)や各部分の洗練を経た後に完成したのが それまでに製作された中で最大の爆撃機となった当機B-36である。第二次大戦の終結には間に合わ なかったが、終戦直後の1945年9月8日に工場から搬出された原型1号機は、それから飛行準備に 1年という長い期間をかけ翌年8月にようやく初飛行を行った。 途方もなく大きな機体を飛ばすため強大なエンジンが必要であったが、設計を変更せずにレシプロエ ンジンのみ強化するのには限度があったため、補助推進機関としてJ47ジェットエンジンを搭載した B-36Dが製作されると、陸軍から独立したばかりの空軍(戦略空軍)の中核をなす機体として重宝 されたのである。 しかし、1950年代になってジェットエンジンが発達してくるとレシプロエンジン搭載の当機では 速力不足や搭載能力への不満などがでてきたため、ジェット戦略爆撃機の選定が行われた。コンベア社 は当機をジェット化したYB-60を提案したが、 ボーイング社のB-52に 破れてしまい、当機も1950年代末には一部の偵察機改装型を除き現役から退いた。
米陸軍が太平洋戦争末期に実戦投入した戦略爆撃機 ボーイングB-29は 日本を完膚無きまでに叩きのめし、連合国軍を勝利へと導いた。だが兵器という物は常に性能向上を目指すも のであり、このB-29も例外ではない。 1945年にボーイング社はB-29の能力増大を目指して、標準型B-29Aの改修を開始した。この 改修型原型に対して米陸軍航空隊は暫定的にB-29Dの名称を与えた。またB-29により大きい荷重 搭載能力を備えるため、B-29に搭載していたライトR-3350エンジン(2,200馬力)よりも 出力の大きいP&WワスプメジャーR-4360エンジンを搭載したB-29改修機もXB-44の名で 飛行試験が開始された。 これら改修機の試験結果による改設計を加えられ、新素材により軽量化された胴体を持つB-29Dを 米陸軍航空隊は200機発注したが、太平洋戦争終戦により発注は60機にまで削減された。この新型B -29Dはエンジンや機体設計に大幅の変更があったため、新たにB-50と呼ばれるようになった。 B-50は爆撃機としての寿命こそ短かったものの、空中給油機や偵察機として改修された機体は19 60年代まで現役として生き残こり、ベトナム戦争を最後に退役した。
イングリッシュ・エレクトリック キャンベラ(English Electric Canberra)は、同社が開発した双発三座 のジェット爆撃機である。 1945年から開発に着手し、最初の試作機A.1は1949年5月に初飛行した。 ジェット機ではあるが、面積の広い直線翼を採用し、最高速度は平凡(高度12,000mでマッハ0.88)だが 低空から高空まで高い運動性を発揮した。 当初の目的であった高高度爆撃機型のほか、低空支援爆撃機・偵察機・練習機などの派生型も生まれ、 イギリス空軍では2006年まで現役であった。 またオーストラリア・ニュージーランド・インド・南アフリカ・アルゼンチンなどにも輸出された。 またA-26の後継機を欲していたアメリカ空軍の目にもとまり、仕様を少し変更しマーチン社でライセンス 生産されたものがB-57として採用された。 B-57などライセンス生産分を含め1,300機以上が造られた。
その2 im10806292 1945年(昭和20年)4月に天一号作戦の一環として、また菊水作戦と呼応して出撃した第一遊撃部隊(戦艦「大和」以下10隻)の第一警戒航行序列をイメージしています あくまでイメージなのでお借りしたMMDモデルと実際の艦船は必ずしも一致してません 時間的には第一警戒航行序列を組んだ4月6日19時45分以降です 全く関係ありませんが、Wikipediaを見ると4月6日に大和では汁粉が配給されたとある一方、別のサイトを見ると4月7日の夜食が汁粉の予定とあり、二日連続で出る予定だったのかどうか少し気になりました 4月6日の第一遊撃部隊の行動 1520 徳山沖出撃 1620 前路掃海部隊の第三一戦隊(花月、榧、槙)を分離解列 1645 B29飛来 1945 第一警戒航行序列(対潜警戒陣形) 2020 之字運動開始(対潜水艦対策) 2020 「磯風」浮上潜水艦らしきものを発見、「矢矧」これを探知 2130 「矢矧」連合軍の通信を傍受 艦長「長官、『磯風』が潜水艦らしきものを確認したのこと。どうやら発見されたようです」 長官「そうか。明日は朝から忙しくなりそうだ……」 〇お借りしたもの 戦艦大和 im2876301 MMD用モブ軽巡洋艦1940セット im5811625 駆逐艦「時雨」1944 im4239863 夕雲型駆逐艦 im3973377 朝潮型駆逐艦1944 im4889276 海面5配布 im10603332 穏やかな月夜 HH3 im5396035 MMD用モブ船演出セットIII im5391224
1936年にフランスの航空機メーカー各社が軍事産業の国有化の一環として国有航空機工業に吸 収された際に、ブロック社の技術陣はお蔵入りになっていた16人乗りの旅客機M.B.160の設 計案をSNCASO(国立南西航空機製造社:Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest)に 持ち込んでいた。この設計案を元に2種類の派生型を開発することとなり、旅客輸送機型のM.B. 161と爆撃機型のM.B.162の開発が同時進行で進められた。 旅客機型原型M.B.161.01は1939年9月に初飛行し、エール・フランス航空から発注 を得たが、その後フランスがドイツに占領されるとフランス工業界はサボタージュを行ったため、そ の影響から生産1号機が納入されたのは終戦後の1945年9月となった。 旅客機型の開発が優先されたため、爆撃機型M.B.162原型の製作は遅れていたが、1940 年6月にようやく初飛行することができた。片持ち低翼単葉、全金属製構造を持つ4発の重爆撃機は 長大な航続距離と大きな搭載能力を持ち、アメリカの B-17などに勝るとも劣らない 性能を示したが、1機だけ完成した原型はドイツ軍に接収されてしまい量産されることは無かった。 ドイツ軍に接収された原型機は、フォッケウルフ社の監督の下で各種のテストが行われ、1943 年からは長距離の秘密任務に従事していたのだが、終戦時スクラップにされてしまったらしい。
次 im10810939 前 im10806292 1945年(昭和20年)4月に天一号作戦の一環として、また菊水作戦と呼応して出撃した第一遊撃部隊をイメージしてます あくまでイメージです 時間的には10:00前後です 実際に日本艦隊と接触したのはPBYカタリナ飛行艇ではなく、PBMマリナー飛行艇です。念のため 4月7日の第一遊撃部隊とその周囲の状況 1000 第一遊撃部隊上空に展開していた戦闘機が帰投。また、艦載水上機を陸上基地へ退避 米第58任務部隊から攻撃隊約300機が第一遊撃部隊へ向け発艦 1016 米軍飛行艇2機が第一遊撃部隊に接触開始 1045 米第58任務部隊からさらに約100機の攻撃隊が発艦 1100 機関故障のため落伍していた「朝霜」が視界外へ消失 米第5艦隊司令官「西方に向かっている?目的地は沖縄ではないのか。これでは戦艦での邀撃は無理だな…」 〇お借りしたものはコンテンツツリーに記載させていただいております
WWII中の1945年1月に、マクダネル社は世界初の純ジェットエンジン動力艦上戦闘機 FH の初飛行に成功した。 その2ヶ月後、同年3月に後継機として本機 F2H Bansheeの開発が開始された。 掲載ページをここにするか「1946本来の時代」のページにするか悩んだが、実戦配備期間が後年まで長いのでこちらに。 F2Hの初飛行は1947年11月であった。部隊配備は1949年。 事実上、アメリカ海軍初の量産艦上ジェット戦闘機である。 大型の機体で運用可能な空母が限られる等の制約もあったが、拡張性があり偵察用カメラを多数携行する偵察機型、機首にレーダーを追加装備した全天候型にも発展した。 またカナダ海軍も1955年から導入し、マジェスティック級軽空母ボナヴェンチャー (Bonaventure・SASでMod公開されている) で運用した。 全サブタイプ合計での生産数は895機にのぼる。 朝鮮戦争に実戦参加したが、戦闘機として前線の空対空戦闘に加わることがほとんど無く、もっぱら偵察機と阻止攻撃・近接支援攻撃機として用いられた。
グラマン J2Fダック (DUCK) は、アメリカ合衆国のグラマン社で生産した水陸両用機。 胴体下部にフロートが繋がったユニークな構造の機体であり、フロート内の空間に燃料や貨物の他、並列のシートに2名まで人員を乗せて輸送が可能だった。尾部には着艦フックを装備しており、空母への着艦も可能であった。1933年4月24日に原型となるJF-1が初飛行に成功してから1945年に戦争の終結によって生産がキャンセルされるまでの長期間にわたって約600機製造された。 J2Fは文字どおりの汎用機として哨戒、海難救助、輸送、連絡、観測、標的曳航、煙幕展開等の任務で活躍した。 1937年2月にはアルゼンチン海軍が 8機、39年11月に1機購入し、アルゼンチン空軍も3機購入している。
ロケット弾を積んで地上攻撃に向かう途中 【P-38から続く一連の静画はこの画の説明文にて完結するのですが、今回の件を考え暫くの間控えておこうと思います。 →この画をUPした後、2019年10月31日に首里城火災がありました。あれから一年経ちますので説明文を戻させて頂きたいと思います。 【F4Uによる地上攻撃の記録映像がありますね。その中に出てくるフリップボードには「OKINAWA 6-15-44」と書いてありますが、1945年の間違いですよね(44年6月だとサイパンですし)。攻撃されているのは首里、後半は嘉手納飛行場でしょうか。近くからの撮影は右横を飛んでいるP-38から、遠景のはTBFからの撮影ですかね。発進シーンにTBF出てきますし。「コルセアのすぐ後ろについて突入していったら、ロケット弾のバックラッシュをまともに受けて墜落しそうになったとか(しお様解説より)」。あんなトコ (CASEVAC)から撮っていたのですねぇ・・。何度か沖縄・石垣方面に行った中で、摩文仁、ひめゆりと共に回りました。残念です。
第二次大戦末期にリパブリック社は P-47サンダーボルトの機体を流用し 軸流ターボジェットエンジンを搭載したジェット・サンダーボルトを設計した。戦時中の急造要請にはうってつけの機体であっ たが、競争機だったノースアメリカン社のジェット・マスタングなどの設計案に比べると見劣りしていた。そのうち戦争が連合 軍勝利で終了しそうな形勢となったためジェット化計画は見なおされ、一から再設計した機体を開発することになった。 再設計のうえ1945年12月に完成した原型機XP-84はジェネラルエレクトリック社のJ35エンジンを搭載しており 翌年9月には原型2号機が時速983km/hの米国速度記録を樹立した。米軍に採用されたF-84B(追撃機を表す記号Pから 戦闘機を表すFに改められた)はサンダージェットと愛称を付けられたが、頑丈さが売りなだけで扱いにくい性格の機体は操縦 士達から酷評されていた。 1950年に後退角主翼を持った改良型F-84Fが開発され、こちらはサンダーストリークと名付けられた。F-84シリ ーズはNATO各国にも採用され、20年に渡ってNATO戦力の重要な一端を担ったのである。