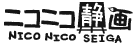32年 を含むイラストが 98 件見つかりました ( 81 - 98 件目を表示 ) タグで検索
2ドアクーペは4シリーズとして独立し、M3はセダンのみになったけど、 スポーツカーではなくなったわけではない。 しかし、32年前の初代と比べて最新型の全長は460mm長くなり、 全幅は225mm広くなり、重量は540Kg重くなって排気量は526cc増加し、最高出力は272馬力向上してる。これが何を意味すると考えるかは人次第...。いや、2ドアと4ドア比較してるのはちょっと無理があるかもしれんがね。
フランスのロワール社は1932年に全金属製応力外皮構造でガル翼式の高翼単葉の単座戦闘機ロワール 32原型を完成させた。フランス航空省は同時期に行った単座戦闘機競作に対して搭載エンジンを指定し たため、同機も他社の機体同様にイスパノスイザ社製エンジンを搭載していた。この原型機は翌33年1月 に墜落して喪われたが、この時には既にエンジンをグノーム・ローヌ社製星形エンジンに変更した発展型と なるロワール45原型機が完成していた。 ロワール社ではロワール45原型機のエンジンを強力なものに換装して時速370キロメートルを発揮さ せたため、同社はこの機体の設計をさらに改良し、34年夏にロワール46原型機を完成させた。この機 体に目をつけたフランス航空省は60機の量産型を発注し、これら量産型にはフランス空軍戦闘機として初 の無線機搭載も行われることになった。 1936年にスペインで内乱が勃発すると、フランス政府は秘密裏に少数のロワール46量産型(生産2〜 6号機の5機)を共和国政府軍へ引き渡したが、2機は短期間のうちに事故で喪われ、もう2機が戦闘で喪わ れてしまっている。フランス空軍への量産型納入は36年11月から始まり、翌37年には第6飛行連隊に 所属する4個飛行隊すべてが当機へ機種転換を完了した。 第二次大戦勃発直前の39年3月になって、すでに旧式化したとの理由から全機が飛行学校や射撃学校へ 移管され、第一線任務から順次退くことになったのだが、ドイツ軍が侵攻した時点でまだ1個飛行体が当機を装 備している状況であった。しかし、ドイツ軍の侵攻を抑えるには非力であったのか、目立った戦果は残され ていない。
スティパ・カプロニ(イタリア語:Stipa-Caproni)は、1932年にイタリアのルイージ・スティパによって設計され、カプロニ社によって製造された実験機である。中空の樽型の胴体の中に、プロペラとエンジンを完全に取り込んだ形状をしたものだった。すなわち、胴体全体が一つのダクテッドファンになっていた。イタリア王立空軍はスティパ・カプロニの開発に興味を示さなかったが、その設計はジェットエンジンの開発への重要なステップになった。
1932年に設立された民間向け小型機を扱うビーチ・エアクラフト社は現在では押しも押されもせぬ 小型機の代名詞となっているが、この最初の双発機を開発したときは、あまり売れるとは思っていなかっ たらしい。 全金属製・軽合金構造のセミモノコック胴体を持ち単葉双発のオーソドックスな6〜8座の座席を有す る機体(ビーチ・モデル18。愛称はツイン・ビーチ)は1937年に初飛行したが、おおかたの予想ど おり最初の生産機はほとんど売れなかった。19 40年になって米陸軍航空隊が幹部輸送機として20機を発注したことが切っ掛けとなり、また第二次大 戦の勃発による一般輸送用や航法・爆撃練習機などとしての需要が一気に高まったこともあって、かなり の数の機体が米陸軍や海軍に供給され、一部は武器供与法により英国へも配備された。また中国は輸入し た当機を軽爆撃機として使用している。 大戦終結後も米軍は当機を使用し続けており、米空軍は1960年代初頭、米海軍も1970年代まで 当機を輸送や連絡任務に使用していた。また世界各国へ輸出された機体(最後の機体は1970年に製作 された)も、結構長い間軍用や民間機として活躍している。
1932年にフランス海軍から出された長距離海洋偵察/爆撃飛行艇の要求に基づいて開発された 機体。1933年12月に初飛行した原型機はグノームローヌ9Kbrエンジン(500hp)を搭載していた が長期間の評価試験により、エンジン出力強化や尾翼設計の変更、機首銃座の廃止が盛り込まれ制式 採用となった。エンジンは主翼上に3基が三角形配置されているが、中央の1基は後方へプロペラを向 けた推進型となっている(上掲写真は機体中央(後方配置)のエンジンが判別しにくく双発機に見え てしまうことに注意)。 制式採用となったものの生産型として製作されたのは7機と少数で、原型機を含む全機がカルーパ を基地とするE7飛行隊に配置された。1939年に第二次大戦が勃発すると部隊は地中海での哨戒 任務に従事することになり、この哨戒任務で半数の4機が戦没した。 生き残っていた4機のうち3機も1940年6月にイタリア軍がおこなった空襲により破壊されて しまい、最後の1機についてもその後消息が語られることはなかった。
来年は申年だね、時間が経つのって早いね。1920年:ねえ木曾…実姉にセクハラ紛いするなんて…覚えてなさいよね1932年:NANO*DEATH*KASADERA CUP1944年:瑞鶴先輩がいないなら私が瑞鶴先輩になればいいんだ!(禁断の匣邂逅)背景撮影地 1920年→岐阜県中津川市 弥栄橋交差点1932年→愛知県名古屋市南区 笠寺観音1944年→宮崎県日南市 日南駅前MMD艦これ他関係まとめ→clip/1522630
【「天にしては神と云ひ、地にしては祇と云ひ、人にして鬼と云ふ」と周礼に書いてある。神、祇、鬼とその名は各々異つてゐるが、共に陰陽の二気が巧妙な作用をして出来上つてゐるので、通じてこれを鬼神とも云ふのである。】 (出典: 新井白石「鬼神論」, (1932年), 「元集」, 「鬼神論(抄)」, 「新井白石集」, 『大日本思想全集 第6巻』, 大日本思想全集刊行会, 9ページ.) https://dl.ndl.go.jp/pid/1880163/1/10 (Shard From Chaos : 332-1da67af75f16)
1932年にフランス航空省が出した新型夜間爆撃機の仕様書に基づいて開発された機体。両大戦の 狭間となる平和な時代(かつ全世界的に不景気な時代)だったため、航空機メーカー各社は数少ない軍 との契約にからむチャンスだとして積極的にこの仕様書へ応え、5社から設計案が提出されることとな った。 ブロック社の提出した設計は全金属製の固定脚高翼単葉双発機で、同時期に英国で開発された ブリストル・ボンベイや ハンドリ・ページ・ハローなどに似た 4座機であった。 審査の結果、ブロック社の案とファルマン社の案(F221) が採用され、33年に量産が開始された(量産型発注は34年とする説もある)。原型機は設計から推定され る最高速度よりも低い能力しか発揮できなかったが、量産型では信頼性の高いエンジンと、秀でた部分も無い かわりに特に欠点も見あたらない無難な機体であると評価され、最終的に200機以上がフランス空軍へ供給 された。また大型機開発の経験がなかったチェコスロバキアにおいても、当機のライセンス生産が行われている。 第二次大戦が勃発した時点では、フランス空軍の機体は全機が訓練用として格下げされていたが、チェコス ロバキア空軍の機体は第一線の部隊に配備されていた。ドイツ軍の侵攻によりこれらフランス・チェコスロバ キアの機体は鹵獲され、ドイツ空軍の乗員訓練やグライダー曳航、一般貨物輸送などに流用されている。なお、 少数の機体はドイツからブルガリア空軍へ供与されている。
映画というより小説一冊読んだような重さが残った。 出来の良い2次創作みたいな映画で35年の間にブレードランナーフォロワーの誰かがもう作ってるんじゃないか、というストーリーだった。
戦間期のソ連戦闘機は、初の国内設計機であるI-1以来ポリカールポフ(ポリカルポフとも)の設計した戦闘機であり、本機もポリカールポフの設計であった。原型は1932年に開発が始められたTsKB-3(ЦКБ-3)で1933年に初飛行した。 本機の大きな特徴となっているのがその翼形で、上翼は左右が分割して胴体に取り付けられたガル翼で、前方視界が大きく取られていた。また下翼は半葉とまではいかないものの上翼よりかなり小さく、翼間支柱もI字型の一張間と洗練されていた。この結果、最高速度はやや低かったが旋回性能は第一級であった。部隊配備は1934年末から開始された。 1937年から改良型のI-15bisの生産に切り替わる。改良点は主翼上翼を通常のパラソル型とし、対地攻撃用武装の追加、発動機の出力強化であった。これにより最高速度の向上と軽攻撃機としての運用が可能となった。 スペイン内戦、ノモンハン事変を始めとして、独ソ戦初期まで用いられたが、スペイン内戦ではCR.32相手にI-16では旋回性能が劣ったため、緒戦では劣勢に立たされた。そのためソ連はI-16の改良型ではなくI-15の改良型I-15ter(後のI-153)を開発することとなる。日本においては、ノモンハン事変で日本の戦闘機にかなわなかったためにI-153が開発されたとする間違った説が流布したが、実際にはノモンハン事変よりも前にI-153は開発され、事変での戦闘にも投入されている。 こうして一線級からは外されたが、独ソ戦開始時もかなりの数が部隊配置されており、主に軽攻撃機として使用された。
1957年(昭和32年)のこの日、 日本の南極観測隊が南極・オングル島への 上陸に成功し、 昭和基地を開設しました。 ----------------------------------------------------------- 【お借りした画像】 南極旗のイラスト【いらすとや様】 ※下ネタや誹謗中傷コメントはお控え下さい※ ※荒らしコメントも厳禁です※ ※変なタグを付けるのもお控え下さい※
ツポレフ設計室が、ソビエト初の重爆撃機である双発爆撃機TB-1(ANT-4、初飛行は25年)、これを小型化した偵察機R-6(ANT-7)に続いて開発した四発重爆撃機。原型機の初飛行は30年末で、32年のメイデーには先行量産型の9機がモスクワでのパレードに参加した。その後大量生産が開始され、5年間に818機が生産された。飛行性能の面ではすぐに旧式化したが、大量生産のノウハウを蓄積でき、多くのエンジニアを育成したことで、後のソビエト空軍の基礎を作ったと言われる。