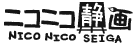66年 を含むイラストが 64 件見つかりました ( 61 - 64 件目を表示 ) タグで検索
フィアット G.91Y(Fiat G.91Y)は、1966年に初飛行を行ったイタリアの地上攻撃機/偵察機である。外観上は前身となったフィアット G.91と似ているが、最大の相違点である双発化と共に全面的に再設計となっていた。形式のYから非公式に「ヤンキー」(Yankee)の愛称で呼ばれた。
自作艦シリーズ200作目突入です。設定は、全長567m・全幅222m・全高234m・重量555555t・6連波動炉心エンジン2基・単発式波動エンジン2基・重力子制御機関2基・艦首200サンチマルチ波動砲4基・主砲55サンチ4連装4基・副砲30.5サンチ3連装5基・2連装大型パルスレーザー砲2基・2連装パルスレーザー砲22基・格納式4連装パルスレーザー砲16基・格納式2連装パルスレーザー砲26基・側部固定式32連装速射レーザー砲2基・側部家電粒子ビーム砲20基・艦首魚雷発射管6基・艦尾魚雷発射管4基・4連装迎撃ミサイル発射管4基・側部小型ミサイル発射管12基・艦底部8連装迎撃ミサイル発射管1基・4連装波動爆雷発射管8基・自立飛行型エネルギーシールド展開装置4基・艦載機20機搭載可・地球防衛軍第一艦隊旗艦兼、防衛軍連合艦隊総旗艦所属・・・です。 元々防衛軍戦力の象徴的存在であったブルーノア型戦闘空母をはじめとする艦艇の多くが抗争の果てに連邦軍所属になってしまったことや、政治的牽制の為に2266年当時の防衛軍第3艦隊旗艦アルデバランが連邦軍管轄に移行してから防衛軍と連邦軍の兵力差が著しいものとなってしまった。早急にこの兵力差を埋められ、且つ防衛軍の新しい象徴となる艦艇の存在が不可欠となり2269年に建造されたのが本艦であった。本艦の建造にあたり、当初はブルーノアをベースにした大型艦が検討されていたが、政治抗争により失われたと思われていた戦略指揮戦艦春藍の設計図がサルベージされたことでこちらをベースとし、現用技術で投入出来るテクノロジーとしてマルチ波動砲、重力子制御機構、自立飛行式のシールド発生装置、半次元潜航機能を有する等、規格外の戦略艦艇として設計・開発されている。また敢えて波動砲は外付け方式にすることで船体艦首にスペースを確保し、そこに重力子制御機構の一部と波動防壁発生装置を組み込むことでマルチ波動砲の機能に貢献している他、ピンポイントバリアと重力制御の併用により強力な衝角機能を獲得している。就役当初から防衛軍第一艦隊並びに連合艦隊総旗艦として君臨、その任を果たしておりまた本艦の存在は兵力差の広がった防衛軍と連邦軍に対する杭の役割を十二分に果たしている。が、水面下での小競り合いの解消には至っていない。因みに正式名称が長いので大戦艦ロキと略称されている。
長崎県諫早市にあった諫早競馬場の場所は江戸時代以降、佐賀藩に仕えていた諫早家の土地であり1938年に民間企業がその場所を借りて1939年にレースが行われました。競馬場は観覧席・投票所・1200メートルの馬場があり売り上げも順調でしたが1941年に日本が太平洋戦争へと突入すると競走馬を徴用され競馬場は軍馬の鍛錬用として使われる事になり、諫早競馬場はそのまま中止となりました。戦後に市民から競馬場の再開を望む声が多くなると1946年に復活し当初は黒字経営になるもその後は低迷、赤字続きとなり1954年に廃止となる。跡地は種畜場として使われ1958年には土地の所有者であった諫早家が諫早市へ跡地を寄贈し、更に長崎国体が開催されることとなり1966年に諫早市から長崎県へ無償で提供され長崎県立総合公園として生まれ変わり現在に至ります。トランスコスモススタジアム長崎と補助競技場の間辺りには1979年に建立された石碑があり、補助競技場の北側を流れる川には競馬場橋と名付けられた橋が架かっています。なお、グーグルマップでの確認となりますが1960年に廃止された上諏訪競馬場(長野県諏訪市)跡地の近くにも競馬場橋という橋があります。 場所:長崎県立総合運動公園 住所:長崎県諫早市宇都町27-1 最寄駅:JR諫早駅 使用モデル よけちさん ナリタブライアン 下校さん スクイズボトル[A]