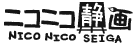7m を含むイラストが 164 件見つかりました ( 161 - 164 件目を表示 ) タグで検索
上がアベンジャーで設定は、全長12.8m・全幅10.1m・全高4.4m・重量22.7t・アメリカ式高出力コスモエンジン1基・機首12.7ミリ機関砲1基・パルスレーザー砲4基(実弾と切替可・ミサイルまたは爆弾積載時は搭載不可)・ミサイル(爆弾)6発・対艦ミサイル(爆弾)4発・アメリカの艦隊を中心に多数配備・・・です。下がテンザンで設定は、全長15.2m・全幅8.7m・全高4.9m・重量25.5t・ツインコスモエンジン1基・機首2連装パルスレーザー砲2基・パルスレーザー砲2基(実弾と切替可・ミサイルまたは爆弾積載時は搭載不可)・小口径パルスレーザー砲4基・ミサイル(爆弾)8発・対艦ミサイル(爆弾)5発・日本を中心にアジアの艦隊に多数配備・・・です。 アメリカ攻撃機系列の先駆けとして設計・開発されたのがこの〝TSA型空間艦上攻撃機アベンジャー〟である。機体特性と運用目的が非常にマッチングした良機であり、艦上戦闘機のキャットシリーズと同様にバランス型で纏まった仕上がりになっている。一方で日本のシンデン等を参考にしたエンジン1基に対して推進ノズルを多数設ける(エンジン1基に対してメインノズル1基とサブ2基)方式をとっており、不必要な大型化を避けつつ宇宙空間での瞬発性を高め、且つ大量のペイロードから繰り出される弾頭の雨という典型的且つ無難な戦術思想はまさにこの機体を表していると言えよう。 ガミラス戦時下における設計・開発で終わった兵器の一つであったのが〝零式空間艦上攻撃機-テンザン十五型〟である。本機も他の多くの日本製航空機同様に開発経緯のそれから型式の括りとして零式の称号が与えられている。元々第二次内惑星戦争で運用された日本製攻撃機の後継機として開発されていたが、戦況の悪化等の理由から22世紀中に空を飛ぶ事は無かった。2240年に日本の艦上攻撃機系列の航空機として正式に運用が開始された本機は設計思想に防弾特化を盛り込んでおり、反面小型化しつつある航空機の中ではやや大きめの胴体となっているが、戦闘時にはその防御力が遺憾なく発揮されている。現在は徐々に新鋭機に活躍の場を譲っているが、信頼性は今も絶大である。 コメントよろです!
設定は、全長128m・全幅23.3m・全高40.7m・重量6458t・単発式波動エンジン2基・主砲12.7サンチ2連装2基・下部10サンチ2連装砲塔2基・75ミリ単装速射砲1基・3連装パルスレーザー砲6基・2連装パルスレーザー砲5基・格納式3連装パルスレーザー砲4基・格納式2連装パルスレーザー砲6基・艦首25ミリバルカン砲2基・艦首魚雷発射管4基・艦尾2連装中口径ミサイル発射管2基・側部8連装迎撃ミサイル発射管・煙突型可動式10連装対空ミサイル発射管1基・下斜方向2連装迎撃ミサイル発射管2基・艦載機12機搭載可・アジアをはじめとする艦隊に広く配備・・・です。 タイが自国製の艦艇を開発する際、連邦の主力艦向けの艦艇として開発されたのがこのローイエット型である。しかし開発当初は重武装駆逐艦として進められていたのだが、列強各国の主力艦艇より性能やコストの面で劣り開発が難航した。そこで艦種を変更、今までにない新しい艦となった。元々駆逐艦規格だったのものに空母同様に航空運用能力を追加。また、武装は一部変更されたもののミサイル類は元の重武装のままであり、艦の大きさに見合わずかなりの戦闘力を有している。特徴は煙突型対空ミサイル発射管であり、艦上方向から右舷方向の可動域が100度あり、状況に応じて角度を調整出来るようになっている(が、この機能が役立った例は極めて少ない)。一つ問題なのは、運用されている国により艦種の分類が定まっていないこと。ある国では護衛軽空母、またある国では航空駆逐艦等とばらばらである為、2260年より連邦が正式に2等級戦術航空運用艦兼2等級駆逐艦とし、便宜上は前者の戦術航空運用艦としている。現在では主力航空運用艦の補佐として前衛で航空隊の補給や特殊航空機運用、潜宙空母化した仕様等があり、徐々に活躍の場を広めている。余談だが、この艦に刺激されたのか、2280年以降に量産が決まっている新フレッチャー改型のバリエーションの中に航空駆逐艦仕様の艦がある。
設定は、全長300.7m・全幅56.4m・全高86.4m・重量79752t・5連波動炉心エンジン1基・小型単発式波動エンジン2基・艦首135サンチ拡散は動砲1門・主砲20.3サンチ2連装2基・12.7サンチ2連装砲塔5基・3連装パルスレーザー砲2基・2連装パルスレーザー砲20基・格納式3連装パルスレーザー砲12基・格納式単装パルスレーザー砲10基・側部大口径フェザー砲2基・・艦首魚雷発射管6基・艦尾魚雷発射管6基・煙突型6連装対空ミサイル発射管1基・側部7連装迎撃ミサイル発射管2基・下斜方向3連装迎撃ミサイル発射管2基・上甲板小口径2連装対空ミサイル発射管4基・下部機雷投下装置2基・8連装ミサイルランチャー2基・艦載機68機搭載可・日本第一航空機動艦隊所属、後→地球連邦第1艦隊航空科所属・・・です。 2203年以降大幅に縮小した防衛軍の軍備拡張案として部分的な自由建造に先駆けて日本支部が建造したカガ(加賀)型宇宙戦艦の元一番艦。量産指向を廃した大型戦艦で後に活躍が期待されていたが就役後間もなく移動性ブラックホールの観測、その後の移住計画の浮上に伴い二番艦のトサ(土佐)と共に一次的に新たな護衛艦艇の実験艦として活用されるようになる。その時に本艦はスーパーアンドロメダ型の部分的な試験運用を担う事となり、戦闘艦の形状を維持しつつ航空戦力の運用にも長けた設計に改変。その後先遣の船団と共にアマールの月へ赴きそこでの任務に従事。然る後に宇宙航空論の影響を受けアカギと共に大改装行い2228年をもってこれを終え、晴れてカガ型宇宙航空母艦として肩書きが変更された。そうして似た境遇にある宇宙航空母艦アカギとは義姉妹として見られる事が多く、洋上艦艇時代のそれとも照らし合わされて広くその存在が知られている。
MSRZー001 Ϝ(ディガンマ)ガンダム 19.7m エゥーゴ製MS MSZ-006 Zガンダムと同時期に開発されていたZ計画の派生機である。 Z計画でほぼ完成をみたZガンダムだったが、一つの難点として複雑な変形機構があげられた。 その変形機構を若干簡略化(ヴァリアントZ系統)(グラビライダー形態)し、性能を落とさず基礎的な機体の質を向上させようと考えたののがコンセプトであり、Zガンダムとほぼ同時期に平行して開発されていた。 背部バックパックをフライトタイプに変更したことにより、変形機構の簡略化(ヴァリアントZ系統)に成功し防御面、火力で言えばZガンダムを上回る。 しかし機動性はデータ上の数値を得られず、またバイオセンサーも搭載していないためアーガマのニュータイプには適応しないということでZガンダムが正式にエゥーゴの主力機となった。 Ϝ(ディガンマ)とは今は使われていない埋もれたギリシア文字であり、開発陣が埋もれたMSであることから名づけた。 またZガンダムとは互換性があるため、Zガンダムの武装を全て流用できる。 (ハイパーメガランチャーなど) 当初は、小惑星ペズン攻略のための、α部隊に配備される予定であったが、急遽カラバの主力となるべくキャリフォルニアベースに送られることとなる。 ビームライフル、ビームサーベルx2,バルカン、グレネードランチャーx2 、シールド、腰部ビームキャノン 登場小説「カラバズストーリー」→http://wato555555.blog120.fc2.com/blog-category-438.html